 455回 455回 |
6月 例会報告 |
|
・日時 2024年6月15日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「海を渡った明治の女性
クリスチャンドクターの誕生とその軌跡」
・講師 遠藤 俊子 氏 |

遠藤俊子氏の研究発表があった。明治初期、アメリカの医科大学を卒業した4人の女医がいた。その4人とは、岡見京、菱川ヤス、須藤カク、阿部ハナで、4人の共通点は、アメリカン・ミッションホーム(現横浜共立学園)の出身であった。
著者がこの書を書くにあたり、彼女たちが歴史に埋もれてしまったのは何故だったのか。明治の激動期女性がアメリカに渡り医者になるには恵まれた条件、あるいは歴史的な条件が重なり合わなければならない。その条件とは何か、という疑問があったという。
本書の構成:
第1章 女医たちの背景―ミッションスクールとプロテスタント
第2章 岡見京とツルー
第3章 菱川ヤスとカミングス
第4章 須藤カク・阿部ハナとケルシー
第5章 4人が目指した医療
終章 女医を生きるーウーマンフッドを超えて
発表者がまとめで次のように記した。4人は「キリスト教における医療―実践的慈愛(身体と魂の癒し)」「治療の成果は神からの賜物」と信じた。それを象徴するものが横浜婦人慈善病院における医療活動であった。ヤス、カク、ハナがこの病院に関わった。
1892年稲垣寿恵子や二宮わか等により立ち上げられた慈善病院に関わったが、政府が貧困層の救済を考慮しない「恤救規則」によって財政が行き詰まり、またキリスト教主義から仏教が力を持つ経営へと変わる中で、慈善病院での活動が意味をなさなくなっていったことが挙げられる。
さらに1900年に開催された第3回宣教師会議において、「医療宣教の中止と教育事業への転換」ということが大きく影響した。
4人の女医と二宮わかたちは、共立女学校において同時期に学んだ仲間であった。それらの人材を繋いで医療伝道に導いたのはツルー宣教師であった。4人の女医たちは、カミング、ケルシー宣教師らを通じてアメリカの医科大学に進み女医になっていった。しかし、日本社会ではそうした先進的な知識、技術を持った人材を生かすことが出来なかった。しかし、私たちはパイオニア的精神をもって活躍した人たちがいたことを歴史に留めなければならいない。
政府が、ドイツ医学を採用したことにより、アメリカ医学を学んだ彼女らが充分に活動できなかったことも一要因と考えられる。
フロアーからは、今まで知られたかったことが発掘されてよかった。
アメリカン・ミッションホームは、医学を志した女性を生むと同時に、保育教育でもこの学校が先駆的な役割を果たしたことが明らかにされた。明治時代におけるキリスト教教育によって、自我に目覚めた女性が盛んにチャレンジした様子を学ぶことが出来た。その生きざまは、現代社会における女性たちに多くの示唆を与えてくれるのではないかと思われる。
(岡部一興 記)
|
|
 454回 454回 |
5月 例会報告 |
|
・日時 2024年5月25日(土) 午後2時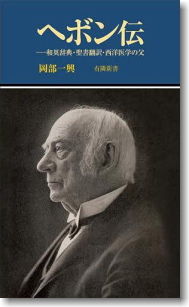
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「『ヘボン伝―和英辞典・聖書翻訳・西洋医学の父』
を出版して」
※ 出版記念会になります
・講師 岡部 一興 氏 |

はじめにヘボンとの出会いを語った。ヘボンとの繋がりは、高谷ゼミに入ったことが挙げられる。しかし、「ヘボン」を出版するとは思っていなかった。
この度、有隣堂から話があって、新書版で一般の方々に、これまでのヘボン研究を総合的に捉えて新たなヘボンを提供することにあった。
1.ヘボンの著作、
2.ヘボン研究、
3.高谷道男のヘボン研究、
4.『ヘボン在日書簡全集』をめぐって、
5.ヘボンの政治的な見方―キリシタンの高札に関係して、
6.女性宣教師に対する考え方、
7.『ヘボン伝』の評価 ― 二つの書評を紹介という形で発表をした。
1867年『和英語林集成』を上海で出版、同時にロンドン版が出て、世界に知れわたった。
ヘボンは辞書を編纂するにあたり、『日葡辞書』、メドハーストの『英和・和英語彙』を参考にしたが、近年木村一氏により『雅俗幼学新書』(1854)を使用していることが分かった。この辞書を基礎に聖書翻訳に入って行った。新約聖書は、結局S・R・ブラウン、D・C・グリーンとヘボンの3人で翻訳、1879年11月3日に完了、1880年4月19日に完成祝賀感謝会を開いた。また旧約聖書の方は、1887年に訳されて、1888年に新栄教会で完成祝賀会が行われた。両方の翻訳に従事したのはヘボンただ一人であった。
ヘボン研究の草分けは、何と言っても高谷道男先生であった。
1938年政府が閣議決定、「教育に関する戦時非常措置方策」で、明治学院に青山学院、関東学院の文科系学部が吸収合併された。
高谷は関東学院から明治学院に移動、図書館長になり、その時ヘボンとの出会いがあり、以後ヘボン研究に熱中した。ヘボン来日100年の時、岩波から『ヘボン書簡集』、1961年には『ヘボン』を吉川弘文館、1976年『ヘボンの手紙』を出版した。「ヘボン書簡集」は215通のミッションレポートの内、121通を翻訳、それらの書簡は、明治維新までの所が多くそれ以後が少ないという編纂の仕方が見られる。
そういうこともあって、全部の書簡を出版する必要があるということから在日33年の中でミッションに送った215通の書簡を集めたのが『ヘボン在日書簡全集』であった。紙面がないので、これ以上叙述できないので、いずれ会報に書くので、そちらを読んで頂きたい。
終わって、懇親会がエビス・ダイニングで行われた。初めに原真由美氏の食前の祈り、鈴木美南子氏の乾杯。自己紹介のあった後、1981年10月から始まったこの研究会の話が中島耕二氏、花島光男氏と岡部からあり、楽しい懇談の時を持った。
(岡部一興 記)
|
|
 453回 453回 |
4月 例会報告 |
|
・日時 2024年4月20日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「関東大震災における内村鑑三と賀川豊彦」
・講師 黒川 知文 氏 (中央学院大学教授) |

1923年9月1日、関東大震災が起こった。死者と行方不明は10万人を越えた。
日本の代表的キリスト者の内村鑑三と賀川豊彦は、大震災に対しどのように応答したのか。両者の比較研究は未開拓であるとして発表された。
大震災の時、内村は63歳、賀川は35歳であった。内村は、1918年1月から再臨運動を開始、1919年6月に再臨運動から撤退、「モーセの十戒」の講演、『聖書之研究』の発行と聖書講演を行い、1921年には「ローマ書講演」、22年には「キリスト伝の研究」の講演を開始した。23年7月、書生数名と軽井沢に家を借りて休養しながら執筆活動、宣教師との交流、講演を行った。9月1日隣家の東大教授小野塚喜平治から大震災の知らせを聞き、9月2日、内村は石原と羽仁元吉と東京に向かった。9月6日から今井館聖書講堂を仙台第二師団小隊に22日まで提供した。9月12日内村宅で礼拝、9月12日には自転車に乗り、東京市内の震災の被害状況を視察、その惨状を見て、「狂はん計り」の心境になった。9月19日には、「来る人毎に悲惨の経験と実話を語る・・・」と述べ、事態の厳しさを実感。
発表者は、内村が10月の『聖書之研究』に掲載された「末日の模型 新日本建設の絶好の機会」として3点が論じられた。
1.罪なき者が犠牲者になった意味は分からないが、「最も甚だしく
痛み給ふ者は天に在ます神御自身であると信じる」
2.「罪人に臨む滅亡は適当の刑罰であって、無辜臨む死は一種の
贖罪の死である」
3.この度の震災は、終末に全世界に起きる災害の「模型」である
「終末ではない、新天新地の開始である」、震災により、「同胞間の同情の泉が開かれた」と言い、最後に「新日本国建設の絶好の機会を与へられた」という。
賀川は、神戸にいたが9月2日『大阪毎日新聞号外』で地震を知るや、海路山城丸で関東に向かった。3日横浜到着、現地を見ると同時に汽車で東京に出て、明治学院の中山昌樹と会い宿泊、5日には赤羽根崎、芝公園、丸の内、神田にある基督教青年会館に行った。9月6日品川から列車に乗り、東神奈川へ行き、材木船東華丸で清水まで行き、神戸に戻った。賀川は、惨状を見て呆然状態にあったが、救援活動を決心。『柱の雲』11月号には、賀川は「おお我等は食狂ふ」と題し震災について述べる。「愛なる神が何故、わが同胞かくは多数に奪ひ、猶、その残れるものを飢餓と、寒気と懊悩によりて苦しめ給ふかを疑ふ為であります。我等は、愛の為に狂ふているのです。」と神に訴えている。賀川は、大震災で一番被害が大きかった本所横川(3万4千人が焼き殺された)に救護テントを張った。「災厄は天罰なりやーヨハネ黙示録の研究―」において、『悪魔は正しきものを一時苦しめやうとも、究極において神は悪魔を追払ふて、正しき者を救ひ給ふのである。さらに黙示録には地震の記述が7カ所あるのを引用し、黙示録によれば、「災厄は信仰を持つ者には勝利であり、悪に対する淘汰である。そして、信仰なきものの地上に這う龍には、災厄は大きな罰である。発表者はは、信仰者の試練について論を進め、賀川もまた内村と同様に社会全体の罪に対する「天譴論」を否定した。「天罰」を用いて、「魂の怠る程度に依って、神の愛の苔ともなれば鞭ともなる」と論じた。
次に賀川の救援活動を扱った。彼は神戸に戻り、援助金を集め一ヶ月で54回の講演を九州、西日本、四国、大坂などで行った。入場料と席上献金7,500円(現在1,668万円)を東京の基督教青年同盟に送った。また『視線を越えて』の執筆で得た莫大な印税などを救援活動につぎ込んだのであった。
発表後、様々な質問と応答があった。何度もノーベル賞候補に上がりながら受賞できなかった理由は何か、1940年渋谷憲兵隊に拘引され、43年神戸の警察署に監禁された。戦争中の賀川についても言及があった。次回会報で、原稿が出るので参考にして頂きたい。
(岡部一興 記)
|
|
 452回 452回 |
3月 例会報告 |
|
・日時 2024年3月16日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「明治期最初の教会オルガンはどんなのであったのかを考察する」
・講師 赤井 励 氏(日本リードオルガン協会顧問) |

各派の宣教師たちは、高札撤去前から少人数ではあるが、聖書翻訳をしながら宣教活動をしていた。楽器を明確に確認できる資料はないが、ヘボンは音楽の愛好家で、居留地39番にオルガンを備えていた。
1873年には日本人医学生が日本語で讃美歌を歌っていた。ヘボンの英語塾を受け継いだジョン・バラの学校で学んだ西村庄太郎は、ミス・ベラ・マーシュにオルガンを習った。のち三共株式会社を創立した。指路教会の長老で、オルガニストであった。
横浜共立学園のL・H・ピアソンは、山手居留地212番の小礼拝堂で祈祷会のオルガニスト、旅行・伝道の際には携帯オルガンも使用していた。ルーミス牧師も讃美歌・オルガンをよく教えた。
当時のオルガンは船に積んで陸揚げしてすぐに使用できるリードオルガン、ハルモニウムであった。しかし,最初は立派な教会堂がなかったので、その使用には困難がつきまとったようである。
長崎県の外海町のカトリック教会では、ド・ロ神父が持ち込んだ最初のフランス製ハルモニウムが残っていた。修復を担当した仁平利三(横浜六角橋教会員)によれば,虫損がひどく,空気漏れを避けるための穴ふさぎや錆びついた木ネジを抜くのに苦労されたとのこと。
新島襄の故郷,群馬県の安中教会では明治期のメーソン&ハムリン社製,意外に重い61鍵のリードオルガンが残っていた。製造番号が2種類あり,年代特定が難しいが1880年代のものだという。横浜海岸教会はパイプオルガンを備えた旧ユニオンチャーチの教会堂を関東大震災で失った。
次の日本人教会の礼拝堂にエオリアン・グランドという高級な吹き出し式リードオルガンを備えた。これがオーウェン・ガントレットの尽力で武蔵野音楽大学楽器博物館に残っている。明治21年より以前は国産のリードオルガンが量産されておらず,楽器販売商社のカタログもメーソン&ハムリン社等,海外製のみが掲載されている。
発表の後、質問感想があった。エドワード・ガントレットと国際結婚した矯風会会長の恒子、ガントレットは英語を教えながら、本郷中央教会にパイプオルガンを入れるのに尽力し、オルガニストとして活躍したことなどが話題となった。
(岡部一興 記)
|
|
 451回 451回 |
2月 例会報告 |
|
・日時 2024年2月17日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「帝室博物館の原田治郎 -美術に託した 異文化 相互理解-」
・講師 小前 ひろみ 氏 (大正大学大学院) |

原田治郎は、美術関係者にもあまり知られていないと発表者はいう。
しかし、Encyclopaedia Britannica14版の数少ない日本人寄稿者で、日本美術の英語解説において欧米で知名度が高かった。原田は、山口県周防大島出身、1893(明治26)年14歳で渡米、カリファルニア州アラメダでサンフランシスコ日本人基督教青年会の長老派教役者ストージ(Ernest
Adolphus Sturge)のもとでキリスト教を学び、カリフォルニア州立大学バークレー校に入学、社会学と文学を専攻。ストージの影響によって、美術方面の探求心が深くなっていった。1905年帰国、名古屋高等工業学校英語科講師、1909年同校教授となる。
1898年10月4日、原田19歳、アラメダのハイクールに通っていた時、サザン・パシフィック鉄道の蒸気機関車の事故に遭った。右脚切断、左手の中指、薬指、小指切断という重傷を負った。義足を付け、その後も必死に生き続けた。
1910年31歳の時、日英博覧会が開催され、この博覧会の広報の重責を担った。
博覧会終了後もイギリスに留まり、事後処理に当たった。またこの年、はじめて『スチューディオ』誌に寄稿、以後6回の連載が組まれ、日本画、描き方、鑑賞法、日本画の動向、教育体制に至るまで解説した。この連載により、原田は欧米の美術愛好家に広く読まれ、生涯にわたり書き続け、その数は116項目に上る。
1917年、原田は帝室博物館至近の桜木町に洋館を建てる。
1919年4月、名古屋教会の長老、東洋紡績取締役服部俊一の長女、初枝と結婚した。初枝は、フェリス和英女学校、女子英学塾出身、江戸千家、御家流香道、細川流盆石を修め、茶道と香道を究め、英語も堪能であった。 原田の私生活をみると、初枝の二人の妹、妹光枝、静枝両夫妻が隣家に引越し、1923年3月体調をくずした服部俊一が名古屋から引っ越し、4家族で毎週聖書の読書会を開き、敬虔な信仰生活が始まったという。
1925年第7回労働総会代表委員付、スイス・ジュネーブに渡航、同年10月正倉院拝観期間中通訳事務嘱託、1926年スイス皇太子グスタフ・アドルフ正倉院観覧通訳嘱託、1927年読売新聞「読売会出版界」に原田記事を掲載、同年5月『the
Gardens of Japan』出版、1929年『Hiroshige』出版、1932年『English catalogue of treasures
in the imperial repository shosoin』等を出版。
1933年11月、原田は「恩師ストージ博士御夫妻の徳を偲び、また私共の心からなる敬慕の情」をこめて、「ストージ会」を結成した。平塚勇之助、瀬上廣成、宮崎小八郎、小林誠ら牧師の他、著名人、医者、実業家など50名が集まった。
1935年、国際文化振興会は、原田をオレゴン州立大学交換教授として講義をし、1936年同大学名誉博士号を授与された。
1955年『Japanese Gardens 』を出版、1963年84歳で逝去。
原田はストージのもとで学び、終生ストージの教えに基づく異文化相互理解に尽力。小前さんは、知られざる原田治郎を発掘し、私たちに明らかにして下さった。原田がキリスト教と出会った教会、受洗を授かった牧師、帰国してからどこで、どのような信仰生活をしたのか等のことについて明らかになると、この研究が大いなる前進となるのではないかという感想をもった。
今後の研究に期待したいと思います。
(岡部一興 記)
|
|
 450回 450回 |
1月 例会報告 |
|
・日時 2024年1月20日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「近代日本のキリスト教保育における先駆的福祉活動に関する研究
-プロテスタント系及びカトリック系の実態を中心に-」
・講師 熊田 凡子 氏、 菅原 陽子 氏、 小林 恵子 氏の共同発表 |

はじめに、キリスト教保育の歴史は、「草創期からのプロテスタント系の保育所・孤児院等の福祉活動の歴史的意義と、カトリック系の保育所・孤児院等の通史的考察とその意義が明確にされてこなかった」という指摘がなされた。
まず、「近代日本におけるカトリック系の児童福祉事業の導入と先駆的福祉活動の実態」のテーマにおいて、小林氏の発表があった。
カトリック宣教開始と再宣教では、ザビエルまで遡る。多くの婦人が墮胎し、女児を殺す間引きの習慣があった。ポルトガル人医師アルメイダは、イエズス会に入会し、育児院を設立、これは日本最初の児福祉施設であった。
次に女子修道会の児童福祉活動としては、神奈川で活動したサン・モール修道会「幼きイエス会」とマリアの宣教者フランシスコ修道会が、日本における幼児教育・保育、キリスト教保育の起源となった。
1875年には サン・モール修道会が築地に孤児院を設立、
1877年には ショファイユの幼きイエズス会修道会、
1878年には シャルトル聖パウロ修道会が現在の函館白百合学園を設立、
1881年には 東京にも白百合学園を設立した。
その後、大阪、盛岡、仙台、横浜、東京などに女学校や高等女学校が設立された。
次にプロテスタント系のキリスト教保育草創期における児童福祉活動の実態の発表があった。プロテスタント系幼児教育・保育の起源は、アメリカン・ミッション・ホームであるという。
次に、プロテスタントの保育に伴う児童福祉施設の紹介が年代順にあった。
1895年「善隣幼稚園」、1897年「キングスレー館 幼稚園」、
1900年「二葉幼稚園」、1904年「神戸保育会」、
1905年「相沢託児園」、1910年「岡山博愛会 保育園」、
1912年「川上幼稚園」が建てられ、
これらの幼稚園や保育園の特徴が説明された。
まとめでは、第一に日本の先駆的児童活動を見ると、プロテスタントはアメリカとカナダが多く、カトリックはフランスを基盤としていた。
プロテスタントの児童福祉は、アメリカやカナダの宣教師が関わり、またアメリカに留学した日本人キリスト者によるものが多かった。
カトリックは、パリ外国宣教会の計画のもとに行われた。
第二には、プロテスタントとカトリックの児童福祉活動では、孤児やその母親に対する救済活動、養護、教育活動という形で展開された。
第三には、プロテスタントもカトリックも、明治期においては教派の支援・援助によって支えられたという特徴を見ることができた。
小林氏がカトリック、菅原氏がプロテスタントの面から発表し、熊田氏はこのテーマで発表する意義と全体のまとめをされた。
何時もの例会では、一人で発表するのに対し、今回はカトリックとプロテスタントの立場から3人の出席による発表だったので、キリスト教保育を多面的に、総合的に捉えることができた点で、今までにない発表となり、ある意味ではシンポジウム的な所が見られた。
(岡部一興 記)
|
|
 449回 449回 |
12月 例会報告 |
|
・日時 2023年12月16日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「横浜クライスト・チャーチ史 1860-2023」
・講師 民谷 雅美 氏 |

民谷氏は、今年の7月『主の平和 ―PEACE OF THE LORD― 横浜クライスト・チャーチ史 1860-2023』を自主出版した(A4版306頁)。この書に基づいて発表された。
横浜クライスト・チャーチ史概略の説明から始めた。
発表内容:
Ⅰ 教会堂建立と牧師招聘
Ⅱ 信徒団の年次申請書と年次政府補助金
Ⅲ 信徒団の政府からの経済的自立
Ⅳ 政府から自立語の信徒団
Ⅴ 2代目教会堂建立
Ⅵ 山手での教会活動
Ⅶ 関東大震災と3代目教会堂向江流
Ⅷ 太平洋戦争
Ⅸ 戦後のクライスト・チャーチ
1860年8月、英国人居留民5人が委員会を立ち上げる。61年10月18日、初代教会堂が横浜居留地101番に開堂。61年12月ラッセル外相がマイケル・バックワース・ベイリーを横浜領事館付牧師に任命。ベイリーは到着後、イングランド国教会の慣例に従って礼拝を実施、しかし、ベイリーは日本人宣教の意志を示さなかった。ベイリー来日以前、主日礼拝の説教を担当していたS.R.ブラウンは失望したと言う。
礼拝は、毎日曜日午前11時と午後4時、駐屯軍のための特別礼拝が午後7時に行われた。信徒団は、年次政府補助金申請書を領事、公使を通して外相に提出、1861年―1866年の年次政府補助金の状況を民谷氏が細かく調査している。1870年6月2日付クラレンドン外相書簡によれば、英国軍が撤退することに備えて、政府の援助なしで信徒団が教会堂を維持できるような財力を持つべきであると勧告された。信徒団は$2000の借入金で側廊を増築、座席数を増やし、座席専用使用料の増収を図ったが、伸びなかった。しかし、日本初のパイプオルガンを4000ドルで購入する等頑張った。
1872年米国聖公会のエドワード・サイル司祭が仮牧師に就任、借入金から解放し政府から経済的自立を目指し、74年6月ロバートソン領事が74年分政府補助金£400を支給、これが最後の政府補助金となった。サイル牧師辞任後、英国聖公会伝道協会(CMS)のパイパー、ファイソン両司祭が主日礼拝の司式を行い、75年12月からギャラット司祭が常勤牧師になった。この当時の「信託証書」には以下の取決めが見られた。
① 座席専用使用料、1座席当たり年間20ドル、6ヵ月以上横浜に住む者が教会会議で投票権を持つ。
② 理事4人は信徒団と英国政府から教会の土地、建物を移譲される。
③ 理事は死亡又は日本出国以外は終生で、理事欠員の場合は教会会議で後任理事を決める。
77年から3年間クライスト・チャーチ内で日本語礼拝をし、日本人伝道を行い、これが横浜聖アンデレ教会の芽となった。1880年アーウィン司祭が就任、1901年6月に帰英するまで牧師を続けた。この時期は財政が安定化し、99年11月新会堂の工事を開始、山手235番の土地に教会堂を建てた。1923年9月関東大震災が起こり、クライスト・チャーチは全てを失った。1927年5月エドウィン・ジョージ・バックル司祭が牧師になり、3代目教会堂の建立を目指し、1931年ヘーズレット主教の司式により教会堂が聖別された。その後、太平洋戦争時代、戦後のクライスト・チャーチについては、発表時間内で説明できなかったが、質問の時間で補われた。
戦時下における日本聖公会は、独立した教団として認められず、主教が九段の憲兵隊司令部に連行されて獄中生活を強いられた。なお、1947年には教会堂が再建されて、英語の礼拝だけではなく、日本語集会による横浜山手聖公会が誕生し、現在に至っている。民谷氏は、英国のPublic
Record Office等の文書を読み込んでクライスト・チャーチの足跡を丁寧に発表されたのが印象に残った。
(岡部一興 記)
|
|
 448回 448回 |
11月 例会報告 |
|
・日時 2023年11月11日(土) 午後2時
・場所 Zoomのみの開催
・題 「明治16年のリバイバルと横浜 ―横浜伝道会社と阿久和教会―」
・講師 山口 陽一 氏 |

ズームによる発表であった。先生がインフルエンザに罹ったが、熱が下がりましたので発表して下さった。
阿久和教会は、1890(明治23)年9月17日、神奈川県鎌倉郡那賀川村阿久和の中丸定右衛門家において、日本基督一致教会の教会として創立された。現在の泉区の「緑園都市」の近くに存在した。
しかし、欧化主義時代が終わり、大日本帝国憲法、教育勅語が発布され天皇国家主義の時代に入り、キリスト教は停滞する時期に入るが、8年足らずのうちに1898(明治31)年7月、大会で阿久和教会が解散するに至った。
その後も、現在の横浜海岸教会とのつながりの中で教会の再興を計っていることも見られるが、不明な点が多いこの教会のことを山口先生が調査して明らかして下さった。
発表内容を記すと、
1.横浜海岸教会のリバイバルと横浜伝道会社
2.横須賀教会の場合
3.横浜伝道会のメンバー
4.阿久和、戸塚、金目への伝道
5.阿久和教会の成立、終りに。 という内容であった。
1883年明治16年横浜海岸教会の初週祈祷会からリバイバルが起こった。これを契機として、悔い改めと信仰の覚醒は欧化時代を背景に全国に飛び火した。
1月4日には伊藤藤吉により三島教会が創立、2月には明治会堂に1600名が集まり、5月には第3回全国基督教信徒大親睦会が開催、群馬、仙台、同志社などで盛んな伝道が行われた。
同年3月横浜海岸教会総会で「横浜伝道会社」が設立、「横浜伝道会社規則」を作成、「各所に伝道者を派遣し及び伝道者志願者を養請する目的」をもって伝道が展開された。伝道地としては、横須賀、阿久和、鶴間、戸塚、原町田、金目村、保土ヶ谷の7ヶ所であった。
1886年7月15日には横須賀教会が創立、初代牧師に伊藤藤吉が収まった。横浜伝道会社から各地に出張されたメンバーは、稲垣信、熊野雄七、山本秀煌、藤尾金六、伊藤藤吉、星野又吉、多田晋、林蓊、原沢紀堂、岡山省三等であった。阿久和では、1885年3月22日名主の中丸定右衛門、その子鶴吉、中丸勇次郎が稲垣信から受洗。
4月5日には、定右衛門の父直吉、素封家の北井要太郎が受洗、8月30日には2人、86年3月3人が受洗、さらに同年12月には18名が洗礼を受けた。
家長が受洗すると、子や親が続くという農村地域における典型的な入信であった。また戸塚矢部町では、1890年矢部基督教講義所が創立されるが、1908年に廃止。平塚の金目村では自由民権運動家の宮田寅治を中心に1888年に日本基督金目教会が建設された。
阿久和は、1890年9月66人の信者を以って創立された。中丸定右衛門の土蔵で礼拝が始まった。しかし、1898年7月に解散をしているが、1906年の『福音新報』をみると、横浜海岸教会の笹倉彌吉牧師が、当教会の伝道地として訪れている。その点から考えて海岸教会の伝道所として継続していたが、何時その伝道所が消えたかのかは不明である。
多くの農村教会が消滅しているが、海岸教会が積極的に出て行って福音を宣べ伝える教会であることが分かった。しかし、それを維持できなかった教会の課題は何であったか、なぜ支えきれなかったか、また戦争が地域に芽生えた教会の芽を摘んでしまったことを指摘された。
発表者の言わんとするところを十分まとめることができないが、後日改めて会報に発表の要旨を依頼したいと考えているので、そちらをお読み頂きたいと思います。
(岡部一興 記)
|
|
 447回 447回 |
10月 例会報告 |
|
・日時 2023年10月21日(土) 午後2時
・場所 横浜指路教会教会堂 (Zoomと併用開催)
・題 「ジェームズ・バラの日本伝道」
・講師 飛田 妙子 氏 |

まず、「バラ一族の宣教」ということで発表。多くの宣教師が来日したが、「宣教がその子孫まで受け継がれた例はそう多くない」といい、その点バラ一族は、バラからマカルピン、モーアというように。子、孫、曾孫まで受け継がれたことは注目に値するという。
バラ一族の研究は、横浜より名古屋地方で多く進められた。ジェームズ・バラの二女アンナの夫R・E・マカルピンが、バラの開拓伝道の後を受けて名古屋を中心として東海地方で伝道、金城教会、金城女学校を設立した。その子J・A・マカルピン(バラの孫)は戦前から宣教を始め、終戦後は1946年に来日、その姉で、バウド・チャンバースと結婚したアンナ・ヘップバーン・マカルピンの息子のラードナー・チャールズ・モーア(バラの曾孫)は、大阪の淀川キリスト教病院のチャプレンを勤めていたという。
次に「ジェームズ・バラの歩み」ということで、
1.誕生から来日まで
2.教会ができるまで
3.日本基督公会の設立
4.日本人牧師誕生・バラ遠隔地伝道に赴くという項目に分けて発表、
同時に海岸教会の長老で、会員の川村洋士氏が画面に発表関係の写真を映し出して下さった。
バラは、セントラル長老教会でフリーマン牧師に出会い、決心を打ち明けた。
ニューブランズウィック神学校在学中、S・R・ブラウンが来校、講演を聞く。
1860年暮、シモンズが宣教師を辞任したため、急遽日本派遣が決まった。

教会ができるまでの箇所では、最初の受洗者・矢野元隆のこと、教会の土地が与えられ、小会堂が建てられたこと、ゴーブル対バラの米国領事裁判で敗訴になり143ドルの賠償金を払ったことなどが述べられた。

日本基督公会の設立の箇所では、3人の蝶者仁村守三、安藤劉太郎、桃江正吉の話が出て、仁村が豊田道二と同一人物であることが国吉栄の研究で明らかになったことに触れた。またタムソンが生み出した東京日本基督公会の設立、横浜公会の新会堂の完成についてと日本基督一致教会の創立について述べられた。

4の日本人牧師誕生の所では、バラのあとを継いだ稲垣信のこと、バラが名古屋伝道を始めること、明治16年のリバイバルにおいてバラが活躍したことなどの話をした。バラは、雨傘と大きな麻袋と、細引きを持ち歩いて野宿をしながら伝道したというので、今では信じられない伝道の仕方である。
最後に井深梶之助の言葉を紹介した。
「言葉は未熟ながらも、燃ゆるばかりの熱心さを以て聖書を説明し、且つ、声涙共に下るといふべき熱誠を以て彼らの為に祈りつつ伝道せらるる事がなかったならば、明治五年三月に日本最初の基督教会は建設せらるることは、恐らくなかったであろう。」と結論付けた。
(岡部一興 記)
|
|
 446回 446回 |
9月 例会報告 |
|
・日時 2023年9月23日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「米国福音教会女性宣教師 G.E.キュックリヒのキリスト教幼児教育
― フレーベル思想と幼児教育のかかわりの中で ―」
・講師 菅原 陽子 氏 |

「本発表は、米国福音教会の初期の宣教、教育、福祉活動について明らかにし、キュックリヒが米国福音教会のミッションを持ち、展開したキリスト教幼児教育について検討したものである」
とこのように発表の目的を述べている。
ゲルトルート・エリザベート・キュックリヒは、1922年に北米の福音教会から派遣されたドイツ人宣教師である。
彼女は、東洋英和女学校幼稚園師範科や草苑高等保育学校、和泉短期大学等の保育者養成に従事した。又保育施設や孤児院「愛泉寮」創設、日本キリスト教保育連盟設立に寄与、日本の幼児教育、福祉に貢献した。
キュックリヒは、1897年シュトゥットガルトのドイツ福音教会牧師の娘として誕生、1908年父の赴任先のベルリンで「リセ」に進学した。
第1次世界大戦で婚約者が戦死、父の勧めでシュトゥットガルトの福音教会のフレーベル・セミナーで学び、1921年幼稚園教諭養成上級教師の国家資格を得た。1922年オハイオ州に船で渡り、英語を習得し宣教師の訓練を受け、その年の10月に来日した。24歳であった。
このようにキュックリヒの略歴と生い立ちを述べた後、
1.米国福音教会宣教師の活動とキュックリヒの教育・福祉実践、
2.アメリカの幼稚園運動の思想的背景と日本でのフレーベル主義教育の展開、
3.フレーベルの思想と教育について発表した。
キュックリヒは、54年に亘って日本に在留、第2次世界大戦下にも帰国せず、山中湖の富士ビューホテルに強制疎開された。日本の幼児教育に貢献、1976年に逝去、享年79。前にも触れたが、キュックリヒが鐘ヶ淵幼稚園に託児部設立、埼玉県加須市に戦災孤児修養施設「愛泉寮」設立、愛泉幼児園設立、愛泉養護老人ホーム設立、「愛の泉」理事長、和泉短期大学教授、西ドイツより一級功労十字勲章を受章。
菅原氏は、「キュックリヒは、人間は神に創られた作品であり、神に創られた人間のとりわけ乳児、幼児期が大切であるという子ども観を持つ。そして、子どものもつ神性を自覚させること、子どもの生命を現わさせ、発展させるために、その時期に即する教育を行うことを教育観とする。それは、ドイツの人間観から来ているとおり、フェレーベルの人間観、教育観と一致している」と結論付けた。
キュックリヒについての研究にさらなる前進がありますように。詳しくは、会報に発表の要旨を掲載しますので、そちらを読んで欲しい。
(岡部一興 記)
|
|
 445回 445回 |
7月 例会報告 |
|
・日時 2023年7月15日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「湯浅八郎の留学体験」
・講師 辻 直人 氏 |

まず、研究の経緯を述べた。一つは留学史研究、二つ目はキリスト教教育史研究をしてきた中で、湯浅八郎の留学を中心にした発表であった。
父治郎は安中藩の商家「有田屋」当主、母初子は徳富蘇峰、蘆花の姉、両親とも新島襄の影響を受け、厳格なクリスチャン・ホームで育った。
八郎は、同志社普通学校卒業時に同志社教会で受洗。卒業後単身留学、1908年8月シアトルに上陸。
1909年には加州リビングストンの奥江清之助の開拓農場で約2年間働いた。
1911年カンサス農科大学に入り、学費を稼ぐため家事労働や皿洗いなどのアルバイトをし、生物学教授から声をかけられ、害虫研究の手伝いをした。
この時の経験がイリノイ大学で昆虫学を専攻する契機となった。さらに大学院で昆虫学を専攻、1920年Ph.Dを取得。州立博物局技師となり、鵜飼清子と結婚。独仏に文部省在外研究員として留学、1924年京都帝国大学教授となる。
1933年滝川事件が起こる。滝川幸辰が中央大学の講演で、無政府主義的な発言をしたことが問題となり、法学部の教授らが辞任、評議員で農学部の湯浅は、この処分に反対した。
1935年同志社第10代総長に就任、学内問題の解決に向けて取り組み、「同志社教育綱領」を起草、建学の精神に務めたが、同志社神棚事件、勅語誤読事件などを通じて総長排斥運動が起こり、任期半ばで辞任した。
1938年、インド・マドラス(現チェンマイ)近郊のタンバラムで世界宣教会議への出席を依頼され、賀川豊彦、河井道らと日本のキリスト教界代表として出席、さらに、その会議報告を依頼され、日本代表としてアメリカへ赴いた。
アメリカ在米中、真珠湾攻撃が起こったが、シーベリーらの助力で捕虜にならず。アメリカに留まり戦争終結の努力をし、抑留日本人の救済に当たった。
1946年帰国、同志社に招かれ、総長に就任、50年国際基督教大学(ICU)の初代学長、62年まで務めた。またキリスト教学校教育同盟理事長、新島学園理事長などを歴任。
発表者の辻氏はいう。「20世紀初頭、全米各地の大学を中心に日本人学生会が組織され、その全国ネットワーク化が雑誌Japanese Studentsの発行によって促進された(1916年)。この一連の動きはYMCAの目指す世界的エキュメニカル運動と呼応するものであった」。
こうした世界的潮流の中で、湯浅は留学時だけではなく、戦中も含めて二度アメリカで過ごしたことが、彼のキリスト教国際主義という思想の形成に大きな影響を与えたという。
(岡部一興 記)
|
|
 444回 444回 |
6月 例会報告 |
|
・日時 2023年6月17日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「象徴天皇 ―『象徴』像の変遷と戦争責任―」
・講師 吉馴 明子 氏 |

吉馴氏は、「天皇」が自分の記憶に登場するのは、幼稚園時代列車で通過する天皇に「旗を振る」ために踏切へ行った時であると自らの体験を述べ、高校、大学へと進み、「憲法」や「日本近現代史」を学ぶ中で、「天皇制」とは何かを考えるようになった。
 Ⅰ.裕仁天皇 Ⅰ.裕仁天皇
1.15年戦争下での裕仁天皇
① 戦時中、裕仁天皇は国民にどのように映っていたでしょうか。
宮城前広場での親閲式、観兵式で天皇が整然と行進し、天皇を中心とする国民の一体感を醸し出した。
②「統帥権」掌握者として―1943年9月日本軍がニューギニア・スタンレ―山脈で敗れると、天皇は勝利の見込みを失った。10月フィリピン・レイテの軍事拠点を失った日本軍はルソンでの挽回を企画したが、殆ど戦わずして総退却、武器も食料もなく餓死であっただろうと言われている。吉馴氏の父は軍医であったが、ここで命を尽きたと父の死を語っている。天皇は戦争を止めるとは言わず、「一撃(後)講話」を主張続けた。終戦を提言したのは近衛一人。天皇はその提言を悲観的な考え方として却下。7月26日日本に無条件降伏を求める米英中首脳によるポツダム宣言に対し、受諾を渋り、原爆が投下され、8月10日の御前会議で「国体護持」を条件に「ポツダム宣言」受諾を決定した。
 2.敗戦後の「背広」の天皇 2.敗戦後の「背広」の天皇
① 天皇のマッカーサー訪問、9月27日裕仁天皇はマッカーサーを訪問。面会時に全国行幸の希望を述べ、マッカーサーは「民主的でよい」と快諾したという。
②「新日本建設に関する詔書」―人間宣言(46.1.1)元旦に出され、天皇の「人間宣言」と呼ばれてきた。天皇による行幸は、神奈川、東京都から始まり、「帽子をチョットあげて国民に応える平服姿の天皇」を国民は歓迎。
 3.象徴天皇 3.象徴天皇
「日本国憲法」で正式に決定―46年3月6日「憲法改正草案要綱」が発表され、5月天皇はマッカーサーに新憲法作成の助力に謝意、天皇制が維持されたことで良しとしたようだ。国会での審議を経て46年11月交付。47年5月3日施行。
ここでの「象徴」であるが、貴族院での審議に参加した南原繁は、「象徴」は法律的には「実体概念」ではなく、何の「機能」も表していない。ただ「儀礼的、修飾的な天皇」に過ぎないと述べた。
大日本帝国憲法では、天皇に「神勅」に由来する「神性」を有する考えを退け、統治権、統帥権も奪われた。「象徴天皇」は、それ自体何の価値もない形式的な存在ということになった。憲法7条に「国事行為」を内閣の助言と承認の下で行う。これが70年代までの通説。
Ⅱ.明仁天皇
歩いたり、はなしたりする「象徴」
1989年1月7日天皇に即位、2019年4月30日退位。
 1.「おことば」と行幸 1.「おことば」と行幸
① 2016年8月の「象徴としてのお務めについてのおことば」はおびただしい数に及んだ。
② 行幸啓を通してのメッセージ ー沖縄訪問、過激派の青年から火炎瓶投げつけられる。
 2.憲法違反―日中・太平洋戦争の総責任者であった裕仁天皇に代わって、平和憲法と「戦後民主主義」の「象徴」となった明仁天皇が国民の「好感」を集めた。しかし、場合によっては天皇の言動が国民に好感を示し、啓蒙するようなものになるとは限らない。歴史的状況の影響を受けやすく、逆の場合もあり得るかも知れない。 2.憲法違反―日中・太平洋戦争の総責任者であった裕仁天皇に代わって、平和憲法と「戦後民主主義」の「象徴」となった明仁天皇が国民の「好感」を集めた。しかし、場合によっては天皇の言動が国民に好感を示し、啓蒙するようなものになるとは限らない。歴史的状況の影響を受けやすく、逆の場合もあり得るかも知れない。
(岡部一興 記)
|
|
 443回 443回 |
5月 例会報告 |
|
・日時 2023年5月20日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「日本人の内面性と国家主義の残存 ―D.Cホルトムの視点から―」
・講師 原 真由美 氏 |
ホルトムはアメリカン・バプテスト教会宣教師で、1910(明治43)年来日。
1907年カラマズー大学、1902年ニュートン神学校を卒業して来日した。短期間で日本語を習得、1914(大正3)年東京学院教授、1927(昭和2)年東京学院と関東学院が合併後も、関東学院神学部の教授を務めた。
1936年関東学院神学部と青山学院神学部が合併、青山学院神学部部長となり、1941年太平洋戦争開戦のため帰国、1962年死去。
彼は、日本の精神的要因と直面する諸問題を明らかにするために神道の研究を行った。その成果として、『日本と天皇と神道』を出版した。
1943年、ホルトムはカルフォルニア州パサデナ短期大学で開催された太平洋問題調査会(Inside of Pacific Relations)において「日本人の内面性」を発表した。
このIPRの呼びかけで「日本人の精神構造」に関する会議が本格化したという。
ホルトムは、どのようなことについて日本研究を続けたかについて以下の項目に分けて発表された。
 1.ホルトムの研究にみる日本の国家主義 1.ホルトムの研究にみる日本の国家主義
古事記や日本書紀にみられる日本の神社や様々な神がどのように変化してきたのか、これらのシンボルが時代と共に変化、非宗教的な機能を持つようになった。
 2.日本人の原始的な性質 2.日本人の原始的な性質
1)人種の優位性の誇張、2)略奪活動への依存、3)日本人の権威に対する考え、4)死の受けとめ方と態度。
 3.アメリカの覇権主義とキリスト教会 3.アメリカの覇権主義とキリスト教会
 4.宣教師の見た日本のキリスト教 4.宣教師の見た日本のキリスト教
1)明治維新後の日本人の指導者層にある和魂洋才、2)教会は外国ミッションから自立し、日本の教会を創る傾向がある。指導者層には日本統治を明治維新の国家主義観で行う傾向、3)封建思想、社会構造、制度による依存体質、キリスト教宣教の個人の自覚的、主体的思考の促しが、国体観から抜け出せない。
5.国会主義の残存
1)アメリカの占領改革―天皇の権威による円滑化、2)象徴天皇制とマッカーサーによる施策の不徹底さ、3)民主主義に対する理念の確立。
最後のまとめとして次のように述べた。日本の戦後の歩みを危惧し、ホルトムが1947年に再版した『日本と天皇と神道』では民主主義の発展と男女同権の成熟度が日本の民主主義の指標であると指摘しているが、日本人の精神性の内面にまで変化が及ばなかったことについても触れている。
戦後の日本統治をマッカーサーの天皇の権威を利用して進められたため「国家」が「家の延長」として理解される共同体的国家観の影響は日本人の精神構造を権威主義的なものにし続けている。また冷戦により、政策の積み残しや「神道指令」にも不徹底さがあり、日本人の精神性にはかつての日本の国家主義観も残存していると考えられる。
(岡部一興 記)
|
|
 442回 442回 |
4月 例会報告 |
|
・日時 2023年4月15日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)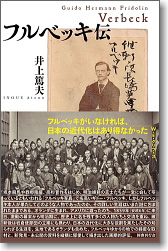
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「フルベキが伝えたかったこと」
・講師 井上 篤夫 氏 |
1830年1月23日オランダのザイストに生まれる。この地域はモラヴィア兄弟団の盛んなところで、ザイストのモラヴィア教会で、弟と妹の3人で堅信礼を受けた。モラヴィア派の学校を卒業すると、ユトレヒト工業学校に入学し工学を学んだ。
井上氏は現地に出掛けてフルベッキの青年時代の手紙を2通入手した。
叔父に宛てた手紙では、音楽を志望したいと告白している。もう1通は、義弟ファン・デュール牧師に宛てた手紙で、フルベッキの苦しみと本音が表れた手紙を発見して叙述している。
22歳の時、アメリカに渡りウィスコンシン州グリーンベイ近くのタンクタウンで職に就き、翌年アーカンソー州ヘレナで架橋工事に携わる。
54年夏、コレラに罹り病床にて誓った。 健康が戻ったら「神の仕事のために身を尽くします」と告白、病気が癒え、姉夫婦が住むニューヨーク州オーバンの街にあるオーバン神学校に入学した。ここで、S.R.ブラウンが牧会していたサンド・ビーチ教会の教会で訓練を受け、1859年3月神学校を卒業、按手礼を受けた。
同年4月会員のマリア・マニヨンと結婚、同年5月7日ブラウン、シモンズと日本に向かった。
ブラウンとシモンズは、11月1日神奈川に到着、フルベッキは同年11月7日に長崎に入り、J.リギンズとC.M.ウィリアムズに迎えられ、崇福寺の広徳院に同居した。1864年長崎奉行所の外語学校語学所の教師となり、65年には大隈重信が佐賀藩の洋学校を立ち上げ、のち済美館と改称、この教師となった。
1866年5月20日佐賀藩家老村田政矩(若狭)とその弟綾部恭に洗礼を授けた。また横井小楠の甥横井佐平太兄弟、日下部太郎、岩倉具視の2子などにニュージャージー州ラトガーズ大学留学に尽力した。
69年には開成学校設立のため上京、大学南校の教頭となり、政府の諮問に応じて重用された。大隈に渡したブリーフ・スケッチが岩倉具視の耳に入り、1871年10月末フルベッキが岩倉を訪ね、スケッチに基づいて相談を受け、日本の近代化のためには欧米の国々を廻ってこの目で見ることが大切であると言った。
同年12月23日岩倉使節団が横浜を出航、欧米の旅に出る。73年開成学校解任、正院翻訳局のお雇いとなり、様々な翻訳を手掛けた。
77年元老院の職を去る。東京一致神学校講師、学習院講師となり、78年日本基督一致教会中会において旧約聖書翻訳委員に選ばれる。この年駿河台の屋敷を高橋是清に頼み売却。同年7月アメリカに帰国。79年9月単身日本に戻る。
83年大阪宣教師会議で、日本プロテスタント伝道について講義し、詩篇やイザヤ書の翻訳をなし、86年明治学院創立に際し、理事、神学教授を務めた。彼は、生涯無国籍であったが、大隈らの力で日本永住を許され、晩年は各所で、伝道し、日本語で説教して人気を博した。
井上氏は、『フルベッキ伝』を書いた感想を述べられた。フルベッキは、自分がどのような境遇にあっても、「さらなる高みに向かって歩む」という姿勢、今自分がやるべきこと、今与えられたことに全力を尽くす生き方に感動したという。作家人生において『フルベッキ伝』を表すことができたことは幸せである、感謝でいっぱいであると結論付けた。これがフルベッキの伝えたかったことであると述べた。
(岡部一興 記)
|
|
 441回 441回 |
3月 例会報告 |
|
・日時 2023年3月18日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「ウクライナ・ロシアの宗教的 文化的背景」
・講師 近藤 喜重郎 氏 |
1.特殊軍事作戦以前の状況、 2.歴史の始まり、 3.キリスト教の東西、
4.歴史の分岐点はどこ?
まず、発表者は、ウクライナ戦争という考えは取らないと言った。
戦争というのは、攻撃されれば、相手の国土に攻撃をかけるのが戦争である。
今回は、ロシアが一方的にウクライナを攻め、ウクライナはロシアに攻撃をかけていないので、戦争というものではない。特殊軍事作戦というものである。
発表内容が広い範囲にわたっているので、発表内容のすべてを述べることはできないので、添付ファイルで送ったレジメを読んで頂きたいと思う次第である。
発表者は、まとめの所で、ウクライナの正教会を、次のように述べている。
◎ウクライナ自治教会(モスクワ総主教庁)、モスクワおよび全ルーシの総主教の監督を認める一派
◎ウクライナ自治教会(コンスタチノープル総主教庁)コンタンチノープルの全地総主教の監督を認める一派、2019年に独立教会と合同
◎ウクライナ独立教会(キエフ総主教庁)キーウの主教の総主教位を主張する一派、2019年にウクライナ大統領の仲介受けたコンスタンチノープル総主教から主張が認められ、その自治教会と合同
◎ウクライナ帰一教会(ユニエイト教会・ローマ教皇庁) ローマ教皇の裁治権を認める一派発表後の質問の時間では、質問や意見が多く出た。
一つは教会と国家の問題、プーチンもゼレンスキーも教会との関りを持ち、熱心に礼拝に出席しているようだ。
それだけ、正教会との関係を無視できないということである。
今回の発表を聞いて、まだ分からないことが多くあるということと、ウクライナの問題は極めて重要な問題なので、再度発表を御願いできないかという意見もありました。
本来は午後2時から始まることになっていたが、不具合が生じて20分も遅れて、やっとズームがつながった関係で、参加したいのに参加できなかった方がいたことをお詫びいたします。
(岡部一興 記)
|
|
 440回 440回 |
2月 例会報告 |
|
・日時 2023年2月18日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)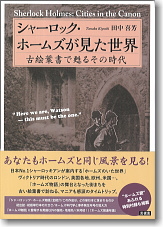
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「シャーロック・ホームズ魅力の世界
― コナン・ドイルは本当にカトリック信仰を
捨てられたのか ―」
・講師 田中 喜芳 氏 |
発表では、1.コナン・ドイルの実像と虚像 2.「ホームズ物語」とは何か
3.「ホームズ物語」に見る聖句 の3点から考察した。
1.では、アーサー・イグナチウス・コナン・ドイルは、名探偵シャーロック・ホームズ・シリーズの作者として知られる。ドイルは当初は熱心なカトリック教徒だった。9人兄弟姉妹の長男(第3子)で、イエズス会系のホッダー校、ストニーハースト校で学び、エジンバラ大学医学部卒業時にはカトリック信仰を棄て唯物論者と称し、心霊主義者となった。晩年は「ホームズ物語」で得た莫大な印税を心霊主義普及のために使った。
2.では、シャーロッキアンはドイルが書いた全60編のホームズ・シリーズを総称して、「ホームズ物語」と呼ぶ。最初の作品《緋色の習作》も2作目の《四つのサイン》も評判にならず、「ストランド誌」に連載した連載短編で爆発的人気を得た。彼がなりたかったのは歴史小説家で、26番目の作品《最後の事件》でホームズを宿敵モリアーティ教授と決闘させ滝に落として殺してまった。非難と復活を望む声が寄せられ、1903年発表の《空き家の冒険》でホームズを復活させた。その後は、二度とホームズを殺すことなく、約40年間にわたりホームズ・シリーズを書き続けた。
3.では、「ホームズ物語」に見る聖句を説明した。《緋色の習作》ではコレヘトの言葉、《バスカヴィル家の犬》ではマタイによる福音書(6:43)、《恐怖の谷》、《ウィステリア荘》ではルカによる福音書(21:19)などの聖句を取り上げた。さらに《最後の挨拶》に登場する聖書の箇所を読み説き、ホームズの言葉に「聖書」の思想が色濃く反映されているのを『ダニエル書』12章11:41-12:11を通じて考察した。この作品は「ストランド誌」(1917年)に掲載されたものだが、本文は、ダニエル書を下敷きに書いていることは明白であった。また「聖書」に登場する奇蹟を心霊主義の立場から擁護しているという。ドイルはカトリックを捨てて、1881年、21歳の時、唯物論者になり心霊主義者になった。
発表後、質問が出るなかで発表者のドイルに対する考え方が明らかになった。カトリックを棄てた要因の一つは、ストニーハースト校での厳しい学校生活だったという。ドイルはカトリックの信仰を棄てたと言いながら、じつは信仰そのものは捨てきれなかったのではないか。また、彼は唯一の神を信じていた。ポーツマス市で医院を開いた頃に彼は心霊主義者になった。
「ホームズ物語」は現在、世界で100以上の言語に翻訳され今も人気が衰えない。また「ホームズ物語」を通して色々なことを調べるのも面白い。事件の中に出てくる料理の研究、彼の手法はビジネスの世界にも応用できる等、自分の関心事から「ホームズ物語」を見るのも面白いという意見も出された。
(岡部一興 記)
|
|
 439回 439回 |
1月 例会報告 |
|
・日時 2023年1月21日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「賀川豊彦の戦争責任告白」
・講師 宮城 幹夫 氏 |
賀川豊彦は、世界に知られた日本のキリスト者である。彼が生涯を通して社会的弱者に尽くした。生活協同組合、労働組合(産業、漁業、農業)、保険組合、医療奉仕等を設立。彼を世界的に有名にしたのは「死線を越えて」の自伝的小説で、多くの言語に翻訳された。
その一方で、彼は愛国的で、天皇制を頂点とする日本の精神風土に崇敬の思いを持っていた。また15年戦争時には、米国、英国を中心とする西洋諸国を批判したことで、戦後の賀川に対する影響力が低下した。GHQによる賀川批判、ノーベル平和賞候補に挙げられながら1955年のノーベル賞推薦委員会が、賀川の推薦を取り下げた。要するに社会的弱者に奉仕した賀川像と日本の封建的な精神風土に敬意を示した賀川像が存在していたのであった。
賀川を評価する場合、戦後日本の学者などが、戦後の価値観で批判している。
当時の文脈を無視して賀川を批判する。賀川の戦争責任告白に対して、賀川の「転向」、「挫折」と判断することは赦されるだろうかと発表者がいう。
賀川を点ではなく、面でとらえる必要があるという。
日本の賀川批判に対し、米国では賀川の愛国的な本性に自国に在る類似性を見出し、彼の本性を超越して評価しているという。またアジア諸国、沖縄に対して、賀川は贖罪の思いを捨てることはなかった。
発表者からは、この研究会で論議する項目を12項目ほど挙げた。その主なものを挙げると、日本基督教団の戦争責任告白、賀川の戦争責任告白、賀川の日本精神風土に対する敬愛、及び敬愛する根拠、賀川の社会的弱者に奉仕する信仰姿勢、国家と教会に対する賀川の聖書理解(ロマ書13章,9章)、賀川の戦中の言動を批判した学者に対する反論、賀川を評価する今日的意味などである。
この発表後、賀川の個人的な戦争責任論と共同体における戦争責任論、日本基督教団戦争責任告白との関係の質問、日本基督教団成立時における賀川の考え方、伊勢神宮参拝に対する賀川の考え方などの質問があった。
また賀川の戦責任に対する結論については、発表者は次のように答えた。
「賀川の愛国的な言動、あいまいな戦争責任告白にも拘らず、米国、韓国で受け入れられている事は、賀川の社会的弱者に仕える働きがあったからだと判断する。その働きは、賀川と同世代の現実主義的神学者のラインホールド・ニーバーが晩年、“強力な人間が、弱者の犠牲において単純に自己の利害を追求していくとすれば、私たちは正義を持たないことになる。”
と述べた。
(岡部一興 記)
|
|
 438回 438回 |
12月 例会報告 |
|
・日時 2022年12月17日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「『横浜海岸教会150年史』の編纂に関わって」
・講師 岡部 一興 氏 |
この教会史に関わるようになったのは、2017年11月の編さん委員会からでした。
まさか、150年史の執筆をさせて頂くとは夢にも思わなかったのであるが、2021年3月上記委員会から依頼されて執筆に加わることになった。小生が担当したのは、J.H.バラが1877年に当教会の仮牧師をやめることになるが、その時から1940年に笹倉彌吉が辞任するまでの63年間を書かせて頂いた。
約半年で資料に当たり執筆しなければならないという急を要した仕事であったので、しっかりしたものが書けたか分かりませんが、奉仕出来て良かったと思っている次第である。
いづれにしても、日本で最初のプロテスタント教会である横浜海岸教会が、このようにして本格的な教会史を編さんすることが出来たのを海岸教会の皆さまと共に喜びたい。何よりもここまで導いて下さった神に感謝する者である。ある意味では、日本の教会史に一石を投じることになったかもしれません。
今回の発表は、2017年に求められて教会史のつくり方、教会史の考え方、教会史の時代区分などについて話をした。
まず、歴史とは現在から過去に向けてくまなく調べる中で、沢山の資料にあたる中で現在から過去の歴史を調べ尽くし、資料を選択して叙述し、将来への決断を生みだすことが歴史を見る目だと考える。そこで教会史は神の民の歴史を叙述するもので救済史を指し示すものと考える。
教会は十字架と復活を信じる群れとして存在する。教会は罪人の集まりで、罪ゆるされた群れでもある。従って、教会はキリストを信じる群れが主から託された宣教の業をどのように行ってきたかを顧みると同時に、これからどのような教会をめざすべきかを志向することになる。その意味で教会史は救済史をめざすものとなる。
時代区分については、編さん委員会で議論したが、何々牧師時代という時代区分ではなく、この教会がどのような組織に加入していたかという視点から時代区分を考えた。その考え方は、改革長老教会にふさわしいものであると考えたからである。すなわち前史から始まって、日本基督公会、日本基督一致教会、日本キリスト教会という区分である。その後、実際に小生が執筆したところを中心に述べさせて頂いた。発表内容についてはレジメを皆さんに差し上げたので、それを読んで頂きたいと考える。
横浜海岸教会は、関東大震災で教会堂が倒壊したが、1945年の横浜空襲では被災を免れたこともあって、比較的資料が整っていることも教会史を書く上で大変助かった。現在、横浜海岸教会の古い資料は、横浜開港資料館に寄託されているので、誰でもこれらの資料を見ることが出来るようになっている。
(岡部一興 記)
|
|
 437回 437回 |
11月 例会報告 |
|
・日時 2022年11月19日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)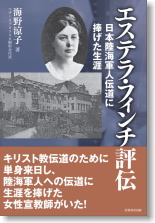
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「エステラ・フィンチ-日本陸海軍人伝道に捧げた生涯」
・講師 海野 涼子 氏 |
海野さんの長年の夢であった『エステラ・フィンチ評伝』が今年の4月に出版された。この本をめぐって発表があった。
フィンチの伝記を手掛けることになった動機は、フィンチ自筆の「祈りの記録」が母親の書棚から見つかったことによる。2002年「マザーオブヨコスカ顕彰会」を発足、フィンチの足跡の旅が始まった。フィンチの故郷ウィンスコンシンとニューヨークにある母校ナイアック・カレッジを訪問した。この学校の創立者シンプソン学長の墓を訪れた。フィンチの信仰を育んだ人物で、「Not I,but Christ」(私ではなくキリスト)の文字が心に残り、フィンチの原点がここにあることを確信した。
この書を書くについては、小檜山ルイ氏の『アメリカ婦人宣教師―来日の背景とその影響』の書籍に触れ、フィンチのような婦人宣教師が19世紀のアメリカで多く生み出されて海外伝道へと押し出されたことを知った。また峯崎康忠の『軍人伝道に関する研究―日本OCUの源流とその展開』の代表的な書に触発された。
フィンチは1869年1月24日ウィンスコンシン州サン・プレリーに誕生、父ジョン、母アンヌ・エステラの3女、幼くして父母を失う。詳細不明、N.Y.のベタニア学院という所で働きながら貧しい暮らしをしていた。
1882年シンプソン学長の神学校(現ナイアック・カレッジ)入学、卒業後Christian Missionary Alliance から超教派宣教師として来日。
1893年2月神戸に来て姫路の日ノ本女学校で教鞭をとった。その後、マリア・ツルーと出会い、角筈で伝道、1896年ツルーの訃報に遭遇、日本滞在5年に及んだ。そこで日本の伝道に疑問を持った。「日本人はキリスト教の思想は受け入れるが悔い改めがない」として、日本に見切りをつけて帰国を決意した。その時、偶然高田に巡回伝道に来ていた佐藤曠二(後の黒田惟信)に出会った。神の道について語りあい、「軍人には軍人の教会が必要である」という話に賛同、フィンチは帰国前横須賀を訪れ、佐藤と再会を約束し帰米した。
1898年約束通り、フィンチは再び来日、1899年9月日本陸海軍人伝道議会を立ち上げ黒田と二人三脚で伝道。聖日礼拝は午後3時、祈祷会、聖書研究会、教理研究会などを行ない、来会者19万人にのぼり、受洗者1000人に及んだ。『軍人伝道義会月報』を発行、ボーイズたちが「日本のために戦死しているのに私が日本人にならないでいられましようか」として、星田光代と改名、日本国籍を取った。
1928年マザーは心臓の病気で召された。享年55。その後、黒田が引き継いだが、1935年黒田も生涯を閉じたので、1936年に解散した。
終わって、様々な質問が出た。それらの質問の中で、フィンチの神学校時代、養女となったがそれは誰かという問いに対し、文献的には実証できないが、有名な大富豪カーネギーの養女になったことが明らかにされた。しかし、彼女はその地位を投げ捨てて軍人伝道に勤しんだ。
フィンチの原点は、ナイアック・カレッジでシンプソン学長と出会う中で、「私でなくキリスト」を覚えての伝道がフィンチの伝道の原点であったという。色々な質問に対し、海野さんが次々に答える発言は祖父黒田惟信から引き継がれた信仰の告白を聞いているようであった。
今後の課題としては、この伝記を娘さんの太田光代さんの手を借りて英文にして発信したいという意気込みを語っていた。今後の健闘をお祈りする次第である。
(岡部一興 記)
|
|
 436回 436回 |
10月 例会報告 |
|
・日時 2022年10月15日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)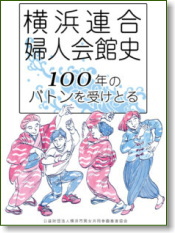
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「横浜連合婦人会館(現、男女共同参画センター横浜南)
の建設に力を尽くしたクリスチャン女性たち」
・講師 江刺 昭子 氏 |
このたび2022年3月、公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会・男女共同参画センター横浜南(フォーラム南太田)編集・発行『横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる』が出版された。同年4月8日の朝日新聞でも「横浜の女性活動1世紀前の礎」と題し取り上げられた。
横浜連合婦人会館は、現在のフォーラム南太田の前身にあたる施設で、関東大震災直後に被災者救援のため横浜の女性団体の有志が「横浜婦人会」を結成、1927年横浜連合婦人会館を紅葉坂(現、西区宮崎町)に建設。3年前、横浜連合婦人会館建設に関わった横浜連合婦人会の女性たちの手書き原稿がフォーラム南太田に所蔵されていることが分かった。
これに解説を加え、今年の3月に200部が発行された。その後デジタルアーカイブ化され、デジタル版はフォーラム南太田のサイトで見ることができる。
江刺氏のレジメによって横浜連合婦人会の活動をみると、1923年10月震災者救援のため市内の女性団体が集まり、事務所を横浜基督教女子青年会の焼け跡に置き、11月には横浜連合婦人会が発会、17団体36人が出席した。12月市内を10区に分け、罹災市民調査、老人、子ども、病人、貧困者に衣類などを支給。1924年6月音楽会を開催、また婦人会館建設計画を立て、10銭募金(現在のお金に換算すると約200円)を開始した。1927年5月宮崎町に横浜連合婦人会館開館式を挙行、バザーを開催。
1928年12月財団法人横浜連合婦人会と改称、規約を作成。会長渡辺玉、副理事長上郎やす、理事岡野まさ、二宮わか、野村美智子、吉川とゑ、赤尾佐久、他の評議員などを含め50名を数える。
財政面では、土地は渡辺玉の息子から土地を譲ってもらい、渡辺銀行から玉の名義で借入をするなど、渡辺家に負うことが大であった。
その後、料理講習会、バザー、家庭衛生講演会、結核予防の講演等様々な活動をしたが、1931年満州事変が起こった頃から自由な活動ができなくなった。
同年11月大日本連合婦人会に加入、1936年8月財団法人横浜市連合婦人会と改称、大日本連合婦人会の傘下に入る。42年には横浜市連合婦人会は解散、横浜市連合婦人会館は横浜市に移譲、横浜市立婦人会館となった。
これらの活動の中で、横浜連合婦人会とクリスチャン女性の結びつきが見られた。加盟団体を見ると、仏教婦人会、基督教婦人矯風会支部、横浜基督教女子青年会、神奈川高等女学校、横浜高等女学校、横浜市女教員会、横浜市産婆会、フェリス、捜真、共立、横浜英和等の女学校、海岸教会、指路教会、横浜メソジスト教会婦人会等23団体が結束した。そのうち13団体がキリスト教系団体であった。
最後に江刺氏が次のようにまとめたように思える。クリスチャン女性と商家の妻たちが立場を越えて連帯し独自の活動をし、連合婦人会館が建設されたのは稀有なことだった。東京連合婦人会では、キリスト教の救援活動が一般的な参政権運動や廃娼運動へと繋がっていったが、横浜ではそのような運動として発展する動きは見られなかった。
感想としては、今まで見たように女性の横の結びつき、連帯によって、このような運動が見られたのは驚きだった。
(岡部一興 記)
|
|
 435回 435回 |
9月 例会報告 |
|
・日時 2022年9月17日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「聖書とヘボン」
・講師 岡部 一興 氏 |
正式には、J・c・ヘップバーンと発音するが、当時の日本人にはヘボンと聞こえた。ヘボンも漢字で平文と書いている。
ヘボンが日本文化にもたらした功績は多くある。それらの中で、聖書和訳に大きな貢献が見られる。
そこで、今回は聖書の翻訳においてどのような役割を果たしのかを考察した。
1872年9月第1回宣教師会議があった。そこで決まったことは、①共同訳聖書の翻訳、②一致神学校、③無教派の教会、それに讃美歌の編纂であった。共同訳による聖書翻訳が実際にスタートしたのは、1874年3月からであった。
ヘボンが来日した最大の目的は、共同訳の聖書を翻訳することであった。聖書和訳をするにあたり、重要なことは翻訳の基礎作りとして辞書を編纂することであった。そのことから7年の歳月をかけて『和英語林集成』を編纂した。
翻訳にあたり困難な問題は、第一にキリスト教の独特な用語をどのように訳すかであった。
キリスト教の「神」「愛」については、中国のビリッジマン、カルバートソンが訳した新約旧約聖書からヒントを得て、「上帝」の訳語から「神」という言葉に訳すことにした。第二には文体をどうするかということであった。当時は日本語が定まっていない状況があり、方言、武士の言葉、町人の言葉、女と男の言葉があり漢文にするか、平仮名にするか、仮名まじりにするかという問題があった。
日本人助手は漢文を主張、ヘボン、S.R.ブラウンは、聖書は誰でも読めるようにしなければならないと考え、「標準語」で仮名まじりの文章にすることを決めた。
1888(明治21)年2月3日東京築地の新栄教会にて完成祝賀会が行われた。新約聖書の翻訳委員が決まってから実に15年の歳月が経過し、新約と旧約聖書の両方に携わったのはヘボンただ一人だった。
それらの翻訳の作業において、聖書翻訳をトータルにみた場合、ヘボンがどのくらい聖書を翻訳したかをみると、驚くべきことが明らかになったのである。新約聖書27巻と旧約聖書39巻合わせて66巻のうち、新約聖書の6割以上、旧約聖書の4割ほどがヘボンによって訳された。
(岡部一興 記)
|
|
 434回 434回 |
7月 例会報告 |
|
・日時 2022年7月16日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂
・題 「ヘボンの子息サムエル
― 書簡を介してみる彼の生い立ちと横浜における文化活動 ―」
・講師 権田 益美 氏 |
サムエルは、J.C.ヘボンとクララの次男として、1844年4月9日アモイで誕生。
ヘボンは、施療、『和英語林集成』』の編纂、聖書の和訳、英語教育など大きな貢献をしている。ヘボンは、在日33年に対しサムエルは40年の長きにわたって滞在したにもかかわらず、ヘボンの陰に隠れてサムエルのことは、ほとんど研究する者がなかった。ヘボンは、サムエルを日本伝道に同行させず、知人宅に託してプリンストン大学に入学したが、大学での勉強も続かず、友人のヤングとの関係もうまくいかなかった。
クララ自身も成仏時の門前近くで、木刀で打たれたこともあり、1861年8月サムエルのために帰米した。1963年3月末、クララは日本に戻った。その後、1865年サムエルは来日し、横浜居留地39番に同居した。21歳の時、居留地にある有数のアメリカ商社であるウオルシュ・ホール商会に就職した。
サムエルは、日本に在住してからスポーツを通じて交流を図った。
野球は、1871年9月30日横浜外国人居留民とアメリカ軍艦コロラド号の水兵による試合が行われ、14対11でコロラド号が勝利している。日米対抗試合では、1876年横浜・東京混合の外国人チームと開成学校の学生チームとの対戦が行われた。開成学校で野球を広めたのはウィルソンであった。横浜・東京混合の外国人チームの横浜在住のプレイヤーには横浜総領事のヴァン・ビューレン、副総領事のデニソンがいた。
ある試合では、そのチームにはサムエルがいて、ピッチャーとして登場、している。ヴァン・ビューレンがアンパイアをつとめたという。34対11で外国人チームが勝利したという。1876年10月20日、35名の会員で横浜ベースボールクラブ(YBBC)が発足した。1881(明治14)年にはサムエルがこのクラブの会長に就任している。
なお、サムエルは、1873年に一時帰国し、クララ・ショーと結婚した。1875年サムエル夫妻は横浜山手238番に家を新築した。ヘボンも39番から山手245番の家に引っ越している。サムエルは、日本郵船に招聘され、1896(明治29)年サムエル夫妻は長崎に移住した。
J.C.ヘボンと比べると、サムエルの客観的資料は実に少ない。今後の研究としては、彼が勤務した会社では、どの程度資料が残っているのか、また横浜ベースボールクラブの側面から調査をするなどして、彼が40年間過ごした日本での生活を調べる必要があるということで、今後に期待したいと考える次第である。
(岡部一興 記)
|
|
 433回 433回 |
6月 例会報告 |
|
・日時 2022年6月18日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂 (出版記念会となった)
・題 「タムソン宣教師と日本の近代化」
・講師 中島 耕二 氏 |
6月例会は、『タムソン書簡集』が教文館から出版されたので発表をお願いした。
中島氏が言うには、ヘボン、S・R・ブラウン、フルベッキはグリフィスによる伝記が出ているが、タムソンは出ていない。長年にわたって日本伝道に尽くしたにも拘わらず、今まで注目されずきたが、日本のキリスト教に貢献した点は大なるものがある。
タムソンは、1935年9月21日オハイオ州ハリソン郡アーチャーで3人兄弟の次男として誕生。父デビッドは大規模農業経営、母サラ・リーは著名な長老教会ジョン・リーの娘。フランクリン大学、ウエスタン神学校(元ピッツバーグ神学校)を卒業後、1862年11月30日ニューヨークを出航、63年5月18日神奈川沖に到着。64年7月横浜英学所で数学を教える。65年10月J.H.バラとアメリカ領事館で外国人集会を開始、日本語教師に小川義綏を雇う。69年2月小川義綏、鈴木鉀次郎、鳥屋だいに授洗。70年6月築地居留地第1回競貸でカロザースと6番を落札。71年2月和歌山藩に招待され、小川義綏を伴い10日間滞在。同藩に配流中の長崎浦上キリシタン(287人)の苛酷な状況を知る。
帰京後、横浜の英文紙にキリシタン釈放を投稿。同年6月17日、ヘボン、カロザースとタムソンはアメリカ政府を通じて日本政府に信教の自由から解放すべしとアピールした文書をアメリカ長老教会海外伝道局に送る。同年6月23日太政官派遣十三大藩米欧使節団の通訳兼コンダクターとして横浜を出発、日本における信教の自由促進に協力。この働きは半年後の岩倉使節団が欧州をめぐるが、キリシタン禁制高札撤廃に大きな影響を与えた。
1872年3月日本基督公会創立、同年9月第1回宣教師会議が開かれ、共同訳聖書、超教派主義教会の形成、一致神学校創立を採択。73年9月日本基督東京公会(現新栄教会)創立。同年12月中会組織の日本長老公会を設立、ヘボン、カロザース、ルーミス、O.M.グリーンが賛成、タムソン、中会設立は本国長老教会規則に違反していると訴える。74年5月メアリー・C・パークと結婚。同年12月タムソン駐日アメリカ公使館通訳官になり、自給宣教師となり、超教派主義教会を志向し、J.H.バラ、S.R.ブラウン等とこの教会形成に動くが厳しい立場になる。75年3月、東京公会のメンバー安川亨、戸田忠厚ら8名が東京第一長老教会に転籍。同年6月築地雑居地南小田原町3丁目、新栄橋袂に新礼拝堂建設、献堂式行う。76年4月長老粟津高明ほかが脱会、日本公会を設立。
1877年9月17日日本基督一致教会創立。アメリカ長老教会、アメリカ・オランダ改革教会、スコットランド一致長老教会の在日ミッション及び日本基督公会と日本長老公会の合同が決定。同年10月3日日本基督一致教会第1回中会開催。同年10月7日開校の東京一致神学校の旧約聖書釈義を担当、80年4月新栄橋教会仮牧師辞任、81年アメリカ公使館通訳兼書記官を辞任、在日ミッションの俸給受ける。82年小川義綏、聖書販売人を連れて長期伝道、84年高知伝道に加わる。
タムソンは在日伝道52年4カ月にわたり、日本伝道に尽くした。主なものを挙げると、1878年小川義綏と桐生教会を創立、88年埼玉県春日部で14人に授洗、89年明星教会(現小石川明星教会)の仮牧師、90年函館教会(現函館相生教会)、紋別教会で説教、札幌北星女学校滞在。93年小川義綏と埼玉県岩槻、粕壁地方伝道、98年東京府角筈講義所で巡回説教、1900年角筈衛星園理事、1914年レバノン教会(旧角筈講義所、現高井戸教会)仮牧師を歴任。1915年5月23日レバノン教会で説教後体調崩し、同年10月29日召天、11月1日新栄教会で葬儀、染井霊園外国人墓地に埋葬された。
PowerPointを使用、対面とズームで行ない、知られざるタムソンの52年間の歩みを顧み、日本伝道に尽くした姿が明らかになった出版記念会であった。
終わって、教会堂において写真を撮った。
(岡部一興 記)
|
※ 写真クリックで拡大します
|
|
 432回 432回 |
5月 例会報告 |
|
・日時 2022年5月21日(土) 午後2時 (Zoomと併用開催)
・場所 横浜指路教会教会堂 出版記念会を行ないます
・題 「日本におけるキリスト教保育思想の継承
― 立花富、南信子、女性宣教師の史料をめぐって ―」を出版して
・講師 熊田 凡子 氏 |
このたび上記の題名の書籍を出版し、それをお祝いして発表して頂いた。
金沢大学に論文を提出、学術博士が与えられた。その論文を書籍化。出版記念会のはじめにおいて、史料収集にあたり南信子のノート238冊、立花富、南信子の保育日誌や記念帖、女性宣教師たちの報告書等との出会いが熊田氏の研究を進展させたという。
研究課題としては、昭和戦前から戦時下および戦後初期におけるキリスト教保育に携わった日本人保育者たちの一次史料を使用してその実態を実証することにあった。そして、一次史料から読み取れる保育者のまなざし、日本のキリスト教保育の実態から保育思想の展開を通史的に実証することにあった。その後、目次を通してこの書の内容の説明があった。
今回の発表では、「戦時下のキリスト教主義幼稚園の実態」というテーマで行なわれた。
発表内容としては、
1.日本のキリスト教主義幼稚園の歴史と特徴
2.戦時下の幼稚園―幼児教育界の国家体制の動向と基督教保育連盟の通達
3.史料に見るキリスト教幼児教育の実態、まとめという形で発表がなされた。
これらのなかで、発表をかいつまんで報告すると、聖和幼稚園では、1943年12月21日終業式後に「基督降誕祭」を行っているが、そのプログラムでは、はじめに宮城遥拝、君が代の国民儀礼の後、園長の挨拶、「礼拝の部」では基督降誕のページェント、その後部屋で「遊びの部」で親睦会を行ったという記録を発表。
一次史料である保育日誌を使って、戦時下のキリスト教幼児教育の実態を明らかにした。戦時下においては名称の変更を強いられた。
東洋英和女学校は、東洋永和女学校と改称させられ、幼稚園も「東洋永和女学校附属幼稚園」となった。このように戦時下にあって難しい経営を余儀なくさせられたが、色々な工夫をして子どもと素直に神さまに祈る姿も見られた。
またキリスト教幼児教育に従事した女性宣教師たちは、戦時下に強制退去を命じられ帰国を余儀なくされた。しかし、戦後すぐさま日本に戻り、戦後復興に尽力した女性宣教師もいたのである。
今回の発表では、教会堂に集まって発表を聞いた方とズームで参加した方があった。両方合わせて27名の参加者を見ることができたが、事務局の手違いで、ズームで参加した方のなかに招待の許可をしなかった方が出てしまい、ズームでの参加が出来なかった方が出てしまいました。
お詫びします。
(岡部一興 記)
|
|
 431回 431回 |
4月 例会報告 |
|
日時: 2022年4月16日(土) 14時~
題 :「会衆主義教会論の日米比較試論 ―会衆主義の日本における展開
としての日本組合基督教会の形成とその史的意義 ―」
講師: 坂井 悠佳 氏 |
坂井氏によれば、会衆主義教会は、オールドイングランドの国教会体制へのアンチテーゼとして形成されたという。
彼らは非国教徒として迫害されオランダやニューイングランドへ移住するものが出た。アメリカの会衆主義教会の初期の指導者は、ジョン・コットンであった。教会の入会に必要な信仰告白には2つあり、教会が歴史的に受け継いできた教義に対する告白、二つ目は回心体験告白がある。
1.日本における会衆主義教会の形成として ー 熊本洋学校と熊本バンドを取り上げた。彼の門下から熊本バンドが誕生し、日本組合基督教会の母体となった点を見ると、ジェーンズの近代日本キリスト教に対する影響力は大きいものがある。ジェーンズは教職ではなく平信徒で積極的に集会を望む生徒を集めて祈祷会を開いた。その教会形成は、宣教師やキリスト教指導者との人格的結びつきから始まる形を取った。熊本バンドのキリスト教受容をみると、小崎弘道の例ではジェーンズの真摯な祈りに動かされて、ジェーンズの「至誠」な「態度」がキリストへと向かわしめた。
2.同志社英学校における熊本バンド ― 約200名が洋学校に学び、そのうち約40名が同志社に移った。彼らは「燃ゆるが如き信仰を以ていたが、所謂神学なるものは少しも知らなかった」という。
3.日本組合基督教会の形成―設立時に定められた「信仰の箇条」は福音同盟会の9カ条からなる教理基準を採用した。しかし、小崎は1892年第7回組合総会で「信仰箇条」に過失あるとして、「信仰の告白」を提案したが否決された。
1894年の大会では信仰告白について協議、いわゆる「組合教会教役者大会宣言(奈良大会宣言)が決議された。これは信仰箇条というより行動規範、道徳を重視したものであった。「奈良大会宣言」は「基督自身の教訓に属する道徳倫理」を内容とし、これこそが「基督教の本領」と位置付けられたのである。ここに、ジェーンズから道徳的にキリスト教を受容した熊本バンド・組合教会は、同志社の自由主義的キリスト教を経て、行動規範・道徳倫理としてのキリスト教信仰を徹底させる方向に向かったと坂井氏は言う。
おわりにー会衆主義の変遷から見えてくるもの。
① 各個教会主義―熊本バンドの面々は、ジェーンズが殆ど会衆派の背景はなかったが、彼を経由して会衆主義の教会論を受容したことが、会衆主義の日本での展開に重要な影響を与えた。
② 何が会衆主義の「日本的展開」をもたらしたのか。
―会衆主義では、各個教会に入れられる時、キリスト者の在り方を重視する。キリスト者として回心している、「聖徒」であると認められた者のみを教会員とするのが会衆主義の教会であるという。
フロアからは、コットンの教会形成、バンドについての質問、日本基督教団における各個教会主義を取る教会の問題点などについての意見や感想が出て有意義な例会になった。
(岡部一興 記)
|
|
 430回 430回 |
3月 例会報告 |
|
日時: 2022年3月19日(土) 14時~ ( Zoomでの開催 )
題 :「鳥屋だいとは誰か ー女性初の日本プロテスタント信者を推理する」
講師: 中島 一仁 氏 |
鳥屋だいは、1869年1月(明治元年12月)、横浜で女性としては最初のプロテスタント信徒、タムソンから洗礼を受けた。
だいは、井上平三郎『濱のともしび―横浜海岸教会初期史考―』によると、鈴木鉀次郎と同じ宮津出身で、金川(神奈川)に居住していたという。
その資料は、「海岸教会人名簿 第一号」に記載されたものである。鈴木鉀次郎は鳥屋だいと同じ日に受洗している。
そして族籍と現在の箇所に宮津出身と書かれている。
その隣の欄に鳥屋だいが記載され、タムソンから同じ日に受洗し、本県平民と記載されているが、宮津出身とは書かれていないのである。
これは井上平三郎の単純なミスであることが判明した。
『植村正久と其の時代』2巻にある横浜海岸教会の「公会名簿」には、鳥屋だいは「金川」在住とされ、横浜海岸教会所蔵の史料「明治三十年三月十日 海岸教会歴史要略」には「神奈川ノ人・・・」と記されている。
この時だいは63歳であった。
だい(多以)の息子で当主である「字本町」の「長三郎」は、安政6年の史料には神奈川町の西之町の百姓で、西之町には、本陣・石井家の2軒隣に「小倉屋」という屋号の「旅籠屋 長三郎」がいる。
つまりだいは長三郎の母になる。
人別帳では、長三郎の家には、長三郎・多以らの家族6人に加え下男1人、下女5人、食売(めしうり)女2人の計14人で、旅籠屋であった。
J.H.バラの妻マーガレットが母国に宛てた手紙に「お婆さん」が、バラの家庭に卵を売りに出入れして、「ババは私たちのバイブル・クラスにも少し興味があるようだ」と書かれている。
神奈川から4マイルの道のりを休まず海岸教会の礼拝にやって来た。
1860年1月初め、ヘボンの妻クララが何時ものように訪れないので訪問したところ、病にかかっていた。肺の不調を訴え、ヘボンに診てもらっている。『S・R・ブラウン書簡集』1874年4月4日、鳥屋台が死亡したので、「明日埋葬することになっている」とある。
享年77。
日本最初のプロテスタントの女性信徒、今まで全く注目されずに来たが、新たな発見と情報を提供された発表であった。
(岡部一興 記)
|
※会員の方が出版された著書を紹介します。
|
 |
『タムソン書簡集』
中島耕二:編
日本基督教団新栄教会タムソン書簡集編集委員会:訳
教文館、2022年3月25日、6,380円(税込) <詳細はこちら>
|
 |
『日本におけるキリスト教保育思想の継承』
熊田凡子:著
教文館、2022年3月9日、8,800円(税込) <詳細はこちら> |
|
|
 429回 429回 |
2月 例会報告 |
|
日時: 2022年2月19日(土) 14時~ ( Zoomでの開催 )
題 :「無償 ・ 虚無 ・ 抽象 ― 知性史の中のささきふさ (1897-1949)―」
講師: 早矢仕 理宇 氏 |
ささきとはどんな女性か。1897年芝区で長岡安平、とらの第6子として誕生。
本名長岡房子、1909年次姉の繁と弁護士大橋清蔵の養女、繁は横浜指路教会最初の女性長老で生涯信仰を貫き通した。
長岡房子は、1910年7月13日、12人の者と共に毛利官治から受洗した。神奈川県立高等女学校卒業後、青山学院英文科入学。在学中からキリスト教系雑誌に投稿、矯風会の活動に関わりガントレット恒の秘書になる。
1923年『改造』『婦人公論』『読売新聞』の後援によりローマで開催された第9回万国婦人参政権大会に日本代表として出席。関東大震災が起こったため帰国。25年芥川龍之介の媒酌で作家の佐佐木茂索と結婚、「ささきふさ」と改めて作家活動をする。ところが26年養父清蔵と27年には芥川が続いて自殺大きな試練を迎えた。
それ以後虚無的になりながら30年のモダニズム全盛期には創作のピークを迎え、その後作品は減るが、戦後『おばさん』『ゆがんだ格子』『街上より』を発表、1949年癌性腹膜炎で死去、享年52。
早矢仕氏は、ささきふさの評価を3つに分けて述べている。ここでは、その一部を紹介する。
①「モダンガール」近代の言説空間における「女」の表象の一つであるという。
正宗白鳥は、ふさが断髪し、洋装で歩く姿をみて「幸福な顔じゃないぜ」と。
紅野敏郎は「ふさ」の墓が田村俊子、真杉静枝と鎌倉の東慶寺にあり、三悪女というが、ふさは悪女とはほど遠い。
管野昭正は『ただ見る』の主人公は女性解放運動に関心があり、ダンスを趣味というが作品内にはそのようなことは一つも書かれていない。
②菅野はふさを「新興芸術派」といい、日本近代文学史上主流ではなく傍流的な位置付けをしている。
③「余技」と位置付ける。廣津和郎に代表された捉え方で、「結局佐佐木夫人の余技に過ぎない」といい、佐光は「ささきふさは、最後まで文学という場で主体としてふるまい得なかった」と切り捨てる。
こうした評価が下されているが、これらの評者は全てのささきふさの作品を読んで評価していないところがある。
早矢仕氏は、ふさの作品をこの発表の中で丁寧に一つ一つ分析する中で、作品の良さを明らかにした。早矢仕氏の発表を通じて学んだことは、「彼女が残した作品のあたらしさは、正当に評価されべきであろう」という指摘が心に残った。また歴史を見る目として、「歴史の再記述」という視点を大切にして叙述しているという考え方。常に新しい見方を想像するなかでふさを捉え直したことに大変教えられる所があった。
この紙面の中で早矢仕氏の発表を的確に表現できないところがある、御容赦を。
(岡部一興 記)
|
|
 428回 428回 |
1月 例会報告 |
|
日時: 2022年1月15日(土) 14時~ 横浜指路教会教会堂
題 :「植村環と戦時下のキリスト教
―日本YWCA機関紙『女子青年界』を手がかりに―」
講師: 服部 直美 氏 |
植村環は、植村正久の娘、日本で二番目の女性牧師となった。YWCA会長、日本基督教団婦人事業局長などを歴任した。
1905年植村正久から受洗、川戸州三と結婚、1919年6月夫が死亡、政久の死を契機に牧師をめざし、エディンバラのニューカレッジ神学校、エディンバラ大学神学部に留学、1929年帰国、自宅にて開拓伝道を始め、1934年4月按手礼を受けた。植村環の戦時下の動向を日本YWCAの機関紙『女子青年界』を手がかりに分析。1941年1月の巻頭言では「国家永遠の計に与りたいものである」、42年1月「東亜解放は歴史に必然である」と。同年1月日本基督教団富田統理伊勢神宮参拝、ホーリネス弾圧事件などが起こる中で、42年11月YMCA、YWCA、日本基督婦人矯風会が日本基督教団所属となった。
43年1月植村環は、戦局の難しさを受けてと題し「東亜の天地にも我等の聖なる旗幟を掲げて御仕え申さねばなりません」と述べた。
1945年8月22日、日本基督教団常務理事会は「報告ノ力」が乏しかったために、
敗戦となったことを深く「反省懺悔」し、天皇の詔勅にあったように「皇国再建」に務めるべし。同年12月、初の常議委員会で、統理は戦争責任については、「余ハ特ニ戦争責任者ナリトハ思はず」と発言。教団内の役職は、交代はあったが辞任や新任はなかった。
東京空襲により植村環の自宅、柏木教会は空襲で焼失。敗戦後の歩みを見ると、46年アメリカ長老教会婦人会の招きで、戦後民間人として初めて渡米、中国、フィリピン等で平和使節として講演旅行を行なった。47年教会堂再建、3人の内親王・皇后への聖書講義、48年国家公安委員、51年日本基督教団離脱、日本基督教会東京中会に加入、世界平和アピール7人委員会を結成、原水爆事件禁止、をはじめ平和活動を推進。
服部氏によれば、『女子青年界』の論調は、ある年代を境に信仰的な論調から、大政を翼賛し皇国キリスト教を推進する論調へと変遷していると分析。戦後の論調は、戦時中のような愛国主義的、戦争肯定的な論説は見られず、一貫して平和主義を唱えた。「罪」と赦しのレトリック。戦争責任を負うことを回避し、平和活動にシフトしたことが、現代日本の問題へと繋がっていないかと指摘した。
(岡部一興 記)
|
|
 427 回 427 回 |
12月 例会報告 |
|
日時: 2021年12月18日(土) 14時~ 横浜指路教会教会堂
題 :「早稲田奉仕園の活動とベニンホフ」
講師: 原 真由美 氏 |
1874年、米国ペンシルヴェベニア州ベナゴンに誕生。フランクリン大学卒業、シカゴ大学に学び、1902年同学で博士号取得。1907(明治40)年アメリカ・バプテスト教会から派遣され、東京学院(関東学院)教授となる。翌年早稲田大学教授で早稲田奉仕園初代理事長安部磯雄を通じて大隈重信と会った。
1904年専門学校令により早稲田大学となり、736名の学生が1907年には6000名と膨れ上がり、1910年には早稲田大学基督教青年会が組織、300名のクリスチャンがいて、教授にも10数名のキリスト者がいた。要請を受けて学生寮友愛学舎を創設。早稲田大学の教授と東京学院長の仕事が重なり、あまりの忙しさで体を壊し、東京学院を辞任。
ベニンホフは、友愛学舎において互いに愛すること、仕える人になり、奉仕の心を養い、何よりも自主性を重んじた。その活動の特徴を見ると、人材育成、聖書研究、社会活動、日曜礼拝を通じて福音を伝える。聖書研究では毎週討論会を行い、有名クリスチャンの講演会、夏季学校、読書会などを開いた。
1913(大正2)年の『教報』には、寮の目的は、クリスチャンホームの環境の中でキリストの品性を身に着け社会に貢献する人材の育成を目指した。
集会内容:①日曜日を除き毎朝6時半より祈祷会、②月、水、金の夜7時より聖書研究、その後一時間英語練習、③月1回の中央委員会、④月1回舎生の親睦会、⑤毎月、文芸会を開いた。
1919年早稲田学寮では13名の学生が洗礼を受け、会員が27名に増加、1921年
J.E.スコット婦人からから5千ドルの寄付を受け、スコットホールの建築が始まった。ベニンホフは、1927年から外交官勤務として太平洋戦争が始まる前までホッジ将軍の政治顧問、また米国への文化使節となり、早稲田奉仕園の財政的支援もあってアメリカで250回の公演旅行を行なった。原氏は、キリスト教社会主義運動に関係する活動が弾圧を受ける中で、奉仕園の初期の活動記録が少なく、明らかになっていない点があるので、今後の課題として、さらに検証する必要があるという。
また、今後の研究として、2020年1月に原氏が横プロ研で発表したバプテスト宣教師D.C.ホルトムの神道研究について研究を進めたいという説明があった。
2020年2月、中島耕二氏がG.W.ノックスについて発表してから対面での例会が出来なかったが、今回教会堂で発表が聞けて良かったという意見が多かった。
今後もできうる限り、対面での研究会を持続したいと考えている。
(岡部一興 記)
|
|
 426 回 426 回 |
11月 例会報告 |
|
日時: 2021年11月20日(土) 14時~ ( Zoomでの開催 )
題 :「戦前のキリスト教主義学校に存在した二つの幼稚園とその保育者たち
――海岸女学校附属幼稚園と青山緑岡幼稚園における幼児教育」
講師: 中村 早苗 氏 |
今回の発表は、幼児教育史学会の紀要に投稿した『幼児教育研究』第14号に基づいて発表がなされた。青山学院は、米国メソジスト監督派教会が派遣した宣教師によって、3つの学校が創立されたものを源流としている。
その学校とは、「女子小学校」(1874年)、「耕教学舎」(1879年)、「美会神学校」(1878年)である。
1876年11月、東京女子師範学校附属幼稚園が創立された。キリスト教系の幼稚園としては、1880年4月、桜井ちかによって桜井女学校附属幼稚園が開設されている。ここで発表された海岸女学校幼稚園は、1892年にWFMS(米国メソジスト女性外国伝道協会)によって設立。この幼稚園では、高野愛子、北米合衆国オハヨウ・ウエスレアン大学などで保育の勉強をして海岸女学校幼稚園で働いた保育者がいた。
しかし、1899年私立学校令と同時に文部省訓令12号が公布されたために築地から青山に移って青山女学院幼稚園と名称を変えた幼稚園は危機に直面することになった。12号は宗教上の教育や儀式を禁じたので、青山学院では、小学校から高等女学校までの教育でキリスト教教育が出来なくなり、その影響から幼稚園の園児が減少し閉園を余儀なくされた。
一方青山学院緑岡幼稚園は、青山学院第6代院長阿部義宗が就任演説でキリスト教教育は根底から考えるべきとして、小学校、幼稚園の設立を計るべきと述べた。その要請に応え、1937年交友会長の米山梅吉が私財を投げ打って青山学院緑小学校を設立、キリスト教教育はできなかったが、田村忠子が理想とするキリスト教保育を実践した
しかし、1944年4月東京都より休園命令が出て緑岡幼稚園は閉園、45年5月25日の空襲で園舎は焼失。終戦後、田村は幼稚園の再開を望んだが、再開されなかったとされてきた。しかし、幼稚園の再開を理事会で決議したことが分かった。
再開しようとする計画があったことが分かったが、1949年の大学開学にともなって寄宿舎整備の問題もあり、大木金次郎の経営方針により幼稚園は再開できなかった。その後、1961年大木によって新たに「青山学院幼稚園」が設置されたのである。
11月例会もズームで行なった。例会後、一人一人が近況を語った。
(岡部一興 記)
|
|
 425 回 425 回 |
10月 例会報告 |
|
日時: 2021年10月16日(土) 14時~ ( Zoomでの開催 )
題 :「ヴォーリズの1930年代 ― 近江兄弟社への改称から」
講師: 西 由香利 氏 |
1880(明治13)年10月28日カンザス州レヴンワースに生まれた。
建築家を目指しマサチューセッツ工科大学に合格したが、家庭の事情により地元のコロラド大学に入学。
1905年1月29日宣教師として横浜に到着、同年2月滋賀県立商業学校で英語教師となる。
同校でバイブルクラスをはじめ吉田悦蔵、村田幸一郎らが出席、1907年八幡基督教青年会館建設したが、伝道活動が原因で学校を解職された。
1908年京都基督教青年会館新築の工事現場監督に就任、同会館内に「ヴォーリズ建築事務所」を開設、また近江ミッションを結成した。
1919年子爵一柳末徳の3女満喜子と結婚。明治学院、関西学院、神戸女学院、教会、住宅などの建築を手掛けた。
1920年メンソレータムの販売権を得る。1933年近江勤労女学校を開校、1934年近江ミッションを近江兄弟社と改称した。
1939年には満州にメンソレータムの工場を造り、1940年近江基督教会は日本基督教団に加盟、1941年日本国籍所得、一柳米来留と改名した。
1942年戦時体制のなかでは軽井沢に留まり、戦後は近江八幡に戻り、近江兄弟社会長に就任した。
メンソレータムが倒産し社名をメンタームに変更したこと、宣教師として来日したこと、建築を学びたかったが、学べず独力で勉強したことなどが紹介された。
今年の1月以来研究会が休止していたが、今回ズームでの例会を行なった。
(岡部一興 記)
|
新型コロナウィルス感染予防のため、
2021年1月から9月までの例会は休止になりました。
|
|
 424 回 424 回 |
12月 例会報告 |
|
日時: 2020年12月19日(土) 14時~ 横浜指路教会 教会堂
題 : 「吉原重俊とS.R.ブラウン」
講師: 吉原 重和 氏 (米欧亜回覧の会理事) |
薩摩藩では、1865(慶応元)年第一次英国留学生19名(内使節4名)を送り、翌年には薩摩藩第二次米国留学生として8名が密航出国、吉原重俊は大原令之助の変名で第二次留学生としてアメリカに渡った。
彼は薩英戦争後、横浜英学所で英語を習い、S.R.ブラウンの母校モンソンアカデミーに入り、イエール大学で法律を学んだ。その間、1866年末から翌年3月にかけて新島襄と出会った。67年5月ブラウン宅が焼失、一旦帰米、69年8月新潟英学校の教師として、キダーと赴任するまで米国NY州オーバンに滞在した。
オーバンのオランダ改革教会のOwasco outlet教会(サンドビーチ教会)において、1869年1月10日大原がブラウンから洗礼を受けた。
彼が受洗した頃に一緒に留学した吉田清成、湯地定基、畠山養成も受洗した。大原は岩倉使節団に新島襄、杉浦弘蔵とともに現地参加、帰国後は明治政府の官吏として働いた。1873年外務省五等出仕、74年大久保利通の清国出張に際し、清国と交渉、条約改正草案の起草に携わる。74年四国高松藩代々の漢学者赤井家の米子と結婚、大久保の口添えだったとのこと。80年2月横浜正金銀行管理長・大蔵少輔、日銀創立委員になり、1882年10月吉原重俊初代の日銀総裁となる。1887年12月18日日銀在任中病気のため死去した。
日本の近代化に寄与した人々の歩みも学ぶことができた貴重な発表でした。
(岡部一興 記)
|
|
 423 回 423 回 |
11月 例会報告 |
|
日時: 2020年11月21日(土) 14時~ 横浜指路教会 教会堂
題 : 「一つの植民地像 ― 聖園農場、坂本直寛を手掛かりに ― 」
講師: 吉馴 明子 氏 (恵泉女学園大学名誉教授) |
吉馴氏は、植村正久研究をされている。この10年来、『福音新報』を調べながら植村の研究を続けてきたという。それが、なぜ坂本直寛なのかと問いかけた。
1902年2月、約5年間浦臼の聖園農場で生活していたところから札幌に出てきて、夏には植村に勧められて伝道者になり、同年11月旭川講義所の伝道師になった。坂本は『福音新報』で編集責任者であった植村の下で日韓関係論を寄稿していた。
吉馴氏は、両者の間には日本のキリスト者が朝鮮において果たすべき務めにおいて何らかの了解があったのではないかという。これを解く鍵が北光社及び聖園農場と「開拓植民」共同体のヴィジョンと経験知にあったのではないかという。
発表内容の項目をあげると、
1.「内国植民地」北海道
2.高知の自由民権運動
3.北海道への開拓入植
4.自由民権・キリスト教開拓植民、の順で発表
高知の坂本直寛、武市安哉は立志学舎で学び自由民権運動に邁進、坂本は1879年愛国社第2回大会で幹事を務め、翌年国会期成同盟第2回大会に出席、81年立志社「日本憲法見込案」作成に従事、87年片岡健吉らと三大建白運動で上京、保安条例違反で逮捕、石川島監獄に収監、2年の間ひたすら聖書に親しみ、大日本帝国憲法発布の恩赦で出獄した。
武市は1892年衆議院選挙で当選、開拓用地払い下げ問題に関わり「市来知の空知集治監訪問」で北海道移住を決心した。高知から北海道への入植者は、武市―土居・坂本の「聖園農場」と坂本・澤本=前田の「北光社」農場の開拓に従事した。この二つの農場の置かれた自然環境、指導者の気質も異なり交代もしたが、これらの農場は指導者の交流もあり、聖園から技術指導者の派遣もあった。これら二つの農場は一つの団体として捉えていいのではないかという。
高知で民権運動が封じ込められた時に、民権運動家の仲間たちは坂本や武市をリーダーとして北海道に移住、原野を開拓して自分たちの共同体を建設しようとした。
発表者によれば、①自由民権運動で結ばれた人間関係、②厳しい自然環境に必要とされたピューリタン的な労働、③聖書のみことばと信者たちの生き生きとしたキリスト教信仰など、3つの要素が組み合わされて「開拓植民によるキリスト教農園共同体」が立てられた。
最後に発表者は、武市=坂本をリーダーとして立てられたキリスト教開拓植民の意義を二つあげた。一つは「内国植民」の流れに逆らう「自由・独立な個人」によって立てられた共同体であった。二つ目は、「アメリカ大陸へのピューリタンの移住にヒントを得て、キリスト教信仰を持つ自立した人々によって造られる自由な天地をモデル」として構想された。
※コロナ禍のなかで、11月27日の東京都の感染者が580名というように、感染者の数が増え続けている状況にあります。今後も、この研究会を継続して行こうと考えていますが、どうか身体に持病を持っている方、自宅で年配者や病気を抱えている方など、また東京から電車に乗って来るので不安だという方がおられ、心配でしたら、どうぞ無理をせず例会を休んで頂きたいと思います。
広い教会堂で席を空けて座り、マスクを着け十分留意して例会を開いていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
(岡部一興 記)
|
|
 422 回 422 回 |
10月 例会報告 |
|
日時: 2020年10月17日(土) 14時~ 横浜指路教会 教会堂
題 : 「『長谷川誠三 ― 津軽の先駆者の信仰と事績』 を出版して」
講師: 岡部 一興 氏 |
長谷川は事業家として教育家として優れた事績を残しているにもかかわらず、歴史に埋もれたままになっている感があった。1977年に「長谷川誠三研究―ある地方事業家の信仰と事績」という論文を書き、これで終わったと考えていたところ、2014年に長谷川家の孫、曾孫の方々から一冊の書物に出来ないかという要望があがった。そこで再度調査をして出版に至った。
長谷川誠三は、1857(安政4)年4月25日に青森県南津軽郡藤崎に生まれ、藤田立策につき漢籍を購読、14歳で主任教授となった。弘前において本多庸一、菊地九郎を中心とする「共同会」なる自由民権運動の結社が誕生すると、長谷川は藤崎地方の委員として活躍し民権運動に邁進。
しかし、1883(明治16)年に共同会が解体すると、次第に政治へのよりどころを失い事業家として活躍することになる。
1887(明治20)年C.W.グリーンから妻のいそと洗礼を受けると、酒造業を廃して味噌醤油製造業に転換、7町5反歩からなる株式会社の大農経営によるりんご園「敬業社」を開設。「敬業社」は今日の青森りんごを日本一にさせるパイオニア的な働きをした。
1899(明治22)年、彼は弘前女学校の校主となってキリスト教教育に勤しみ、藤崎銀行設立、一大倉庫の建設、青森県野辺地での雲雀牧場の経営、秋田県小坂鉱山の開発、石油の重要性に目をつけ、日本石油の大株主となって活躍、社会事業への支援を惜しまずサポートし、1913(大正2)年に北海道、東北地方に大凶作が起こると、20万円を投じて約1000トンの米を買い付け、各地で福音講演会を開き、米を配布して窮民を救った。
その後、1906(明治39)年長谷川誠三は信仰上のことから藤崎メソジスト教会から、一小教派なるプリマス・ブレズレンへと離脱、1910年弘前女学校の設立者の名前は消えて本多庸一に変更された。この派は現在同信会と言い東京都中野に本部がある。
彼は首藤新蔵や浅田又三郎との出会いを通じて、プリマス派の信仰に揺さぶられ藤崎教会を離脱した。この派は万人祭司主義をとり教会制度、教職制度を否定、教職と信徒の区別がない。
第二には礼拝を重視、聖霊に導かれながら御言葉が語られ毎主日聖餐に与り、第三には聖書の深い学びを特徴とする。長谷川はそうした万人祭司主義を徹底させる群れの信仰を見た時に、これこそが自分が求めていたキリスト教であるとして、メソジスト派を退会することになった。
(岡部一興 記)
|
|
新型コロナウィルス感染予防のため、
2020年3月から9月までの例会は休止になりました。
|
|
|
 421 回 421 回 |
2月 例会報告 |
|
日時: 2020年2月15日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「横浜指路教会第二代仮牧師・ジョージ・W・ノックス」
講師: 中島 耕二 氏 (横浜プロテスタント史研究会会員) |
George William Knoxは、1853年8月11日ニューヨーク州ロームに誕生。
父のWilliam Eaton Knoxは長老教会牧師、母はAlice Woodward Jenkes Knoxと言い5人兄弟姉妹の3男であった。
ジョージはハミルトン大学卒業後、1877年にオーバン神学校を卒業、同年5月Anna CarolineHolmesと結婚、翌6月按手礼を受領。同年9月29日SFを出航、10月20日に横浜に到着。横浜居留地39番に住み日本基督一致住吉町教会の仮牧師に就任、バラ学校の教師となった。
1881(明治14)年東京の築地居留地27番に移転、築地大学校の教師(バラ学校80年に築地居留地7番に移転、築地大学校と改称)となり、82年9月から東京一致神学校の教授。
83年芝露月町教会で洗礼を受けた李樹廷(イ・スジョン、漢文から福音書をハングルに翻訳)の受洗に立ちあった。
84年12月には、高知伝道に参加、翌年5月高知教会が創立、自由民権運動家の片岡健吉、坂本直寛たちを洗礼に導いた。
86年明治学院創立理事会議長、同学院英語神学部教授、帝国大学講師を歴任。
1887(明治20)年一時帰国、88年プリンストン大学から神学博士号を受領、同年10月北陸伝道に尽力、92年日本アジア協会副会長となり、93(明治26)年1月高知伝道に参加するが、6月19日帰国。94年ライ教会の仮牧師、翌年12月牧師となる。96年にはユニオン神学校講師、99年2月同神学校教授に就任。1906年ユニオン神学校の校長を代行、1912年アジアに講演旅行に出かけ、同年4月25日ソウルで急性肺炎のため客死した。
他に『福音新報』によるノックス評、ノックスに思想的影響を与えた思想家・哲学者に関する発表があった。
(岡部一興 記)
|
|
 420 回 420 回 |
1月 例会報告 |
|
日時: 2020年1月18日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「太平洋戦争後のアメリカの日本への宗教政策
―バプテスト宣教師D.C.ホルトムの影響―」
講師: 原 真由美 氏 (関東学院大学講師) |
ホルトムは、1884年7月7日ミシガン州ジャクソンに生まれた。カラマズー大学、ニュートン神学校を卒業後、1910年10月23日来日、41年3月20日まで約30年にわたって、日本伝道に尽くした。
来日後水戸地区担当の宣教師として働き、東京学院の教師、14年同学院長、日本バプテスト神学校、関東学院で語学、神学の教師となり、36年青山学院に神学部の授業を委託したことから青山学院の神学部長を務めた。彼は古事記、日本書紀、万葉集などを研究し、さらに明治以降の日本思想の中心をなしたと思われる神道に関心を持つようになり、幾つかの書を出版した。
The Political philosophy of Modern Shinto. Dissertation 1922。
The Japanese Enthronement Ceremonies ( 日本の即位儀礼) 1928。
Modern Japan And Shinto Nationalism 1943 『日本と天皇と神道』。
太平洋戦争敗戦後、天皇制はアメリカによって大きな変革がなされた。
連合軍最高司令官総司令部は天皇を中心に置いた国家主義的体制が太平洋戦争を引き起こした原因であると見ていた。
ここにホルトムは、45年9月22日「日本の学校における国家神道に対し、米合衆国軍政当局の採用すべき特別政策についての勧告」として宗教政策を担当する民間情報局(CIE)に送り、これを軍政当局が採用、「神道指令」となって発表された。
1.日本の教育制度の欠陥に精通し改革に賛同する文部大臣の任命
2.神格化された天皇観の修正、御真影奉儀式の廃止、教育勅語の検討
3.教科書の改訂(神話的・非神話的材料の除去
4.神社の強制参拝の禁止
5.神祇院の廃止と神社管理の文部省への移管
結論的には、民間情報局の宗教班担当者W.K.バンスは「神道指令」の作成に日本の宗教に精通するアメリカン・バプテスト宣教師ホルトムの研究成果を採用したのであった。
「神道指令」をまとめた宗教班担当者のなかにホルトムと、バンスの宣教師の存在があったのである。
※ 例会の後、馬車道にある生香園(中華)で懇談の時を持った。
(岡部一興 記)
|
|
 419 回 419 回 |
12月 例会報告 |
|
日時: 2019年12月21日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「1930年代のキリスト教学校と国家主義:
―明治学院と同志社の事例から―」
講師: 辻 直人 氏 (和光大学) |
発表内容は、1.ラマート事件の真相と影響、2.湯浅八郎と同志社事件であった。
ラマートは、1893年にオハイオ州ランカスターで生まれ、1919年米国長老教会海外伝道局より派遣、福井で宣教活動された後23年より明治学院高等部教授に着任、38年帰米まで聖書教育、英語教育等に力を注いだ。
35年12月高輪警察署に出頭を求められ2回にわたって取調べを受けた。
Herald Tribuneでは「裕仁への中傷で公判へ、東京で出版物を編集する長老教会宣教師,不敬罪で尋問、国外追放の見込み、ラマートは天皇侮辱の意図を否定」、他に『明治学院百年史』の記述、The Evening Bulletinの記述等を紹介、ラマートの見た天皇制国家、日本の学校教育、30年代キリスト教学校教育をめぐる動き、当時の明治学院の様子、キリスト教学校への不満について触れた。明治学院長事務取扱ホキエ宣教師が御真影を受入れ礼拝堂の一角に奉安室を作った苦渋の決断の話、その後矢野貫城が戦時統制下において取った動きの話があった。
「湯浅八郎と同志社事件」では、八郎は1890年父治郎、母初子の商家の長男として群馬県安中に誕生、新島襄より洗礼を受けた。
1908年より24年まで在米、イリノイ州立大学大学院でPH.Dを取得。24年京都帝国大学農学部教授、33年滝川事件が起こる。法学部教授滝川幸辰の論文が自由主義すぎるとされ、鳩山一郎文部大臣が京大に免官を要求、免職になった事件であった。35年同志社大学第10代総長に就任、配属将校らと衝突した。
イリノイ大学での経験、同大学YMCAとの関わりの話があった。八郎は就任にあたり「自由にして敬虔なる学風の樹立を提唱して運営にあたった。しかし、就任早々神棚事件、同年7月学生によるチャペル籠城事件、同年11月予科教授逮捕事件等が起こった。
37年2月「同志社教育綱領」を制定、「同志社は教育ニ関スル教育勅語並詔書ヲ奉戴シ」という文言を入れ、同志社の教育方針を時流に合わせることによって危機を脱する試みをした。
当時のキリスト教学校では、配属将校が学校に配属されていたが、意に沿わないと将校が引き上げることがあった。配属将校が引き上げることは廃校を意味していたので、そのことをいつも留意しなければならなかった。これらの事件を通じて総長の排斥にも至り、同年12月に辞任。
38年12月には世界宣教会議に日本代表として出席、米国に渡り平和を中心としての講演をする等の活動をした。日米開戦中も米国に留まり在米日本人のための活動をしていたという発表があった。
(岡部一興 記)
|
|
 418 回 418 回 |
11月 例会報告 出版記念会 |
|
日時: 2019年11月16日(土) 14時~ 横浜指路教会
研究発表: 小檜山ルイ
「『帝国の福音 ― ルーシィー・ピーボディとアメリカの海外伝道』
をめぐって」 |
出版記念会、小檜山ルイ著「『帝国の福音―ルーシー・ピーポディーとアメリカの海外伝道』(東京大学出版会)をめぐって」という題で発表があった。
ピーポディーは、1861年カンザスのベルモンテに生まれNY州ロチェスタで育ち20歳の時ノーマン・ウオータベリと結婚、インドでバプテストの宣教師の妻として5年間伝道、夫の死去によって帰国。バプテストの婦人伝道局で働き2人の子どもを育てた。
その後、23歳年上の商人ヘンリ・ピーポディーと結婚、2年後死去、遺産の3分の1を得て裕福な未亡人として海外伝道に捧げた。
1901-1902に女性による海外伝道50周年の祭典を提案、成功を収めた。また1920年東洋の7大学建築基金募金キャンペーンを打ち出して、女子大学を設立。
19年禁酒法成立、翌年女性の参政権が成立するが、それらに尽力した。しかし酒はたしなむもので、禁止をする必要はないという禁酒法改正の為の全米女性団との対決があり、結局33年に禁酒法廃止となる。
アメリカ帝国主義の時代にピーポディーが海外伝道推進者としてどう生きたか。どのような役割を果たしたのか、財閥ロックフェラーと海外伝道との結びつき、第一次世界大戦を契機にアメリカの海外伝道の動きが停滞、凋落していくのは何故なのかといった話があった。
『帝国の福音』は、98年春ロックフェラー・フェローとしてアメリカに過ごしたのが契機となり、2010年にピーポディーの日記を発見、そこから本格的にこの書に挑んだ。終わって小檜山先生をお祝いするためのお茶の会があり、楽しい時を過ごした。
(岡部一興 記)
|
|
 417 回 417 回 |
10月 例会報告 |
|
日時: 2019年10月19日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「岡見京と縁の人びとーツルー夫人を中心として―」
講師: 堀田 国元 氏 (一般財団法人機能水研究振興財団理事長) |
2016年に『ディスカバー岡見京』なる私家版出版、その後新資料の発掘があって、新たに編集した本を出したいということで、調査中である。
今回「岡見京と縁のある人びと」というテーマで、ツルーと結び付けて発表された。
岡見京は、アメリカ留学第一号女医であった。1884年岡見千吉郎と結婚、同年9月に夫がミシガン農科大学に留学すると、その3カ月後に京も留学。
岡見は中津藩士岡見清通の次男として生まれた。京はペンシルバニア女子医学大学に留学、89年に卒業後慈恵医院に就職、婦人科主任として活躍するが、92年退職、ツルーの経営する「衛生園」に移った。
一方ツルーは、1874年に来日、現在の横浜共立女学校に奉職、76年原女学校へ移動、78年新栄女学校、81年桜井女学校の実質的な経営者となり、その後90年に桜井・新栄女学校が合併し女子学院が誕生、93年衛生園と看護学校設立に着手。岡見京は家族とともに衛生園に移住、96年にツルーが亡くなるが、胃潰瘍を患ったツルーを看護した。
ツルーの遺志を継いで赤坂病院のホイットニーの協力を仰ぎ衛生園の認可を得るために奔走、赤坂病院の分院として認められたが、1906年に閉鎖。この場所にレバノン教会が誕生、現在の高井戸教会である。
ツルーの墓は青山墓地にある。久ぶりに津田一路先生が出席。先生は高井戸教会の会員で体調面から例会に出席できないが、今回出席できた喜びとレバノン教会やツルーのことなど、心に沁みる話をされた。
(岡部一興 記)
|
|
 416 回 416 回 |
9月 例会報告 |
|
日時: 2019年9月21日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「平和のこころ ―キリスト教平和学から考える戦争、平和、
そして和解―」」
講師: 豊川 慎 氏 (関東学院大学) |
はじめに1.キリスト教平和学とは何か。平和学からの問いかけがなされた。平和学の誕生から平和学の目標を述べられた。
その目標は、「平和」という価値を追求し暴力なき世界を目指し、暴力の連鎖を生み出している構造的歪みを矯正することにある。ヨハン・ガルトゥングは平和とは暴力の不在を言い、暴力には戦争、武力紛争テロなどの「直接的暴力」と貧困、経済的格差、差別、環境破壊、人権侵害などの「構造的暴力」がある。
ユネスコ憲章には、戦争は人の心に中に生まれるので、心の中に平和の砦を築かなければならないという。またロマ書5:1に記されたイエス・キリストへの信仰を通して得られる神の平和について、神と人との和解などについて述べられた。
その後以下に掲げた2から5のことについて話しが展開された。
2.キリスト教思想史における戦争と平和。
3.赦しと和解―キリスト教思想から考える罪責告白。
4.日本のキリスト教会の戦争責任―「戦争責任告白」から「平和責任告白」。
5.キリスト教平和学の課題。
2では、キリスト教は戦争をする事が許されるのか、正当な戦争と平和主義について、初代教会時代から古代ローマ帝国時代における戦争の問題、中世における戦争の問題、宗教改革とそれ以後のキリスト教会における戦争観についての説明があった。それから正当な戦争の条件と基準に触れ、現代の諸問題について述べられた。
3では、和解への4段階があり、悔い改め、赦し、自己に他者の場を設けること、記憶の癒しがある。4では、15年戦争下のプロテスタント教会の戦争協力への実態を述べ、5では、キリスト者の平和への関わり方についての話があった。これからの課題として、過去の歴史に学び、再び戦争を呼び起こすことのないように、平和を作り出す主体として、個々人、教会、大学の役割が問われている。そして平和へのキリスト教教育の大切さを強調された。
横浜指路教会壮年会、婦人会、横プロ研の共催で行われ、市内の教会等にも呼び掛けた。
(岡部一興 記)
|
|
 415 回 415 回 |
7月 例会報告 |
|
日時: 2019年7月20日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「日本組合基督教会の制度的・思想的 「源流」をさぐる」
講師: 坂井 悠佳 氏 |
日本のキリスト教がどのように受容され、どのような展開を見せたかという問題関心から発表があった。
1.近代日本に伝来したキリスト教の背景としてのニューイングランド神学について。
2.近代日本におけるキリスト教の特色―日本組合基督教会の場合についての発表があった。
ここでいうニューイングランド神学は、19世紀前半の第二次信仰復興時代を指している。独立戦争後西部開拓が進み、合理主義、啓蒙主義の影響から19世紀フロンティアの拡大、個人の信仰復興、伝統的キリスト教からの解放が進展した。神と人間との関係においては、神さまが道徳的に支配し、神と人間とのつながりにおいて罪の理解、原罪ということをあまり言わなくなり、教会がなくても救われるといった教会論の希簿化が生まれた。来日宣教師たちの神学思想にも二つの考え方が現れ、ニューイングランド神学の立場、いわゆるニュースクールとオールドスクールの両方の宣教師が来日するようになった。
2、の組合教会の場合では、道徳宗教としての受容は、ピューリタンに代表されるように道徳的に正しいことをしているので救われるといった信仰の捉え方が出てきたのである。その後の展開の個所では、同志社英学校の教育、新神学の流入、奈良大会宣言(1895年日本組合教役者大会宣言書が出る)、国家とキリスト教の問題、三教会同(キリスト教が神道、仏教と同列になり国民道徳に奉仕する宗教を受け入れる)といった問題に同志社英学校の教育、新神学の流入を扱った。
(岡部一興 記)
|
| ※会員の方が出版された著書を紹介します。 |
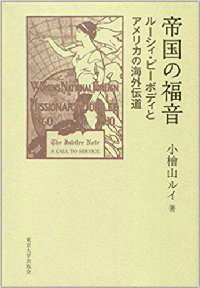 |
小檜山ルイ
『帝国の福音 ルーシィー・ピーボディとアメリカの海外伝道』
東京大学出版会、2019年1月、8,800円+税
|
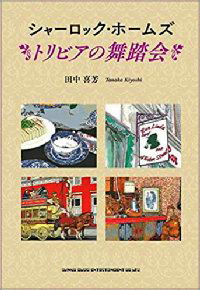 |
田中喜芳
『シャーロック・ホームズ トリビアの舞踏会』
シンコーミュージック・エンタティメント、2019年6月、1,500円+税 |
 |
江刺昭子+かながわ女性史研究会編
『時代を拓いた女たち かながわの112人』
神奈川新聞社、2019年7月、1,400円+税 |
|
|
|
 414 回 414 回 |
6月 例会報告 |
|
日時: 2019年6月15日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「植村正久の生い立ちをめぐって -評伝叙述の充実のために-」
講師: 中島 一仁 氏 |
植村正久の人となりについて、『朝日日本歴史人物事典』では、「安政4(1858)年~大正14(1925)年。明治大正期のキリスト教思想家、牧師。幼名道太郎。謙堂、桔梗生などと号した。家禄1500石の旗本の長男として上総国山辺郡武射田村(千葉県東金市)に生まれる(一説に江戸芝露月町)。大政奉還により生家が窮宇し、貧困の中で幼年期を過ごす。明治1(1868)年、一家で横浜に移った。-
- -略」。主に植村の横浜に出て来るまでの足跡を辿った。
先行研究では、植村正久の父(?十郎)を「家禄千五百石の旗本」と叙述、植村の評伝を書いた雨宮栄一は「徳川旗本千五百石の家系に属す」と慎重な表現をしている。
《生まれから横浜修学期まで》の個所では、『植村正久と其の時代』Ⅰが載せる植村の系図によると、8代目正房(政之助・庄右衛門)、9代目正武(政之助・五郎八)、10代目(?左衛門、?十郎)11代目正久となっている。同書には正武に嗣子がなく、遠山左衛門尉景元2男啓次郎が「第十代目であると名乗る」。
『遠山金四郎家日記』では、景元長男景鳳が植村五郎八の養子となり啓次郎、庄右衛門を名乗るが安政2年(1855)年死去。もう一人の庄右衛門も1856年に死去。その後梅之助(元治2・65)が跡継ぎになる。従って梅之助が継いだので、?十郎が継いだということはない。
では植村?十郎はどういう身分であったのかというと、梅之助の屋敷に住む当時で言う「厄介」であった。当主でも殿様でもなかった。正久の母は、「上総国武謝田村の医を業とせる中村家」の生まれとしているが、母は江戸の武家屋敷での奥女中奉公ではなかったかという。また植村家が横浜に出てきて養豚業をしたことにも触れた。中島氏は、厄介の庶子であった植村が明治維新によって解放された面があったという。
本発表では、原資料を見て語ることの重要性と再度植村の足跡を洗い直す必要があると感じた。
(岡部一興 記)
|
|
 413 回 413 回 |
5月 例会報告 |
|
日時: 2019年5月18日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「M.E.キダーとE.S.ブース」
講師: 岡部 一興 氏 |
フェリス女学院は、日本で一番古い女学校としてよく知られている。と同時に日本キリスト教史の上でも注目されてきたミッションスクールである。そこで、学校を開いたキダーと学校を育て安定化させたE.S.ブースを対比させる形で発表がなされた。
1.伝道することは神から託された使命である : 1620年メイフラワー号のピルグリム・ファーザースから始まって、キリスト教がどのようにアメリカにおいて定着していったかを語った。そうした中で、1859年から多くの宣教師が来日し、1882年のプロテスタント在日宣教師大会までのところでは、313人の宣教師が来られ、女性宣教師が男性をしのぎ、186名にのぼった。
2.キリストの福音を知らない人々のために役立ちたい : キダーの動機は、教育を通して自らが体験した福音を伝えたいというものだった。1870年9月クララ・ヘボンから4人の生徒を引き継いで学校が始まった。79年ミラー夫妻帰米、81年フェリスを辞し、伝道に専念することになる。
3.E.S.ブースの登場 : 1879年12月長崎に来日し、伝道したあと81年12月にフェリスに着任、41年の長きにわたって校長の任にあった。副校長エミリー・ブース夫人とともに学校を運営した。教育に関する考え方は、女子は男子と同じく教育を受けるべき、キリスト教を根底に教育をすべき、単にキリスト的なるに止まらず、真に日本的教育をもたらすべきだとした。
キダーがなした女子教育は、新しい自由な女性の生き方を身をもって示し、近代日本の教育にインパクトを与えた。ブースは夫人とともにキダーが蒔いた種を育てた。高度な教育内容を堅持しながら高等女学校とせず、各種学校に甘んじて独自の道を開いた。その後、質問や意見などがあった。
(岡部一興 記)
|
|
 412 回 412 回 |
4月 例会報告 |
|
日時: 2019年4月20日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「義和団の再来?1920年代の反キリスト教運動と中国キリスト教会」
講師: 朱 海燕 氏 (明治学院大学講師) 氏 |
まず、中国におけるキリスト教の歴史ということで、キリスト教伝来を4期に分けて発表。
①唐の景教、②元王朝、③明王朝末期・清王朝初期では、イエズス会によるローマ・カトリック伝道、④1807年からプロテスタントの宣教―中国の近代化に貢献ということでその概略を述べた。
次に、1920年代の反キリスト教運動のテーマで発表があり、4つに分けて説明された。
①1910年代の思想の準備段階では、国家建設には宗教は要らないという点から民国初年の孔教の国教化運動・袁世凱の帝制活動、陳独秀、胡適らの新文化運動があった。
②最初の段階―1922年「非基督教運動」が展開され、ジョン・モットの世界キリスト教学生同盟第11回会議に対しての反対運動があった。これに対しキリスト教側からは、広東の『真光雑誌』を刊行して反論、応戦した。
③第二段階 ミッションスクールが攻撃対象となり、中国は学校が必要な時代であったが、同年8月には「非基督同盟」が再結成されるなど、反キリスト教終期キャンペーンが掲げられた。
④第三段階 北伐の勢いに乗って教育権回収に乗り出す。1925年には、5.30事件が起こり、6月省港ストライキが始まると、広東は全国革命の中心地となり、北伐を開始、南京を占領、蒋介石が南京国民政府を立ち上げた。
このような発表に対し、1913年にモットが来日、全国協同伝道が展開されこれを契機に教勢が上昇したが、中国ではどうだったのか、また現代中国のキリスト教の現状はどうなっているのか等の質問があった。
現代の中国は、貧富の格差が大きく、キリスト教の教勢も上がっている。三自愛国教会、中国天主教愛国会のように政府公認の教会がある一方で、政府が認めない家庭教会もある。共産党は教会の勢力拡大を恐れ、色々の手を使って抑えている。
(岡部一興 記)
|
|
 411 回 411 回 |
3月 例会報告 |
|
日時: 2019年3月16日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「物語風坂田祐」
講師: 海老坪 眞 氏 |
海老坪先生は、2017年に『物語風 コベルの生涯』を出版、同年11月の例会で発表された。
コベルは、1943年12月20日フィリピンのパナイ島の山奥で日本軍によってコベル一家等15人が虐殺された。その後、先生の仲間から「コベルを書くだけでなく、坂田院長の本を出したらどうかね」と言われて、今回出版したのが『物語風坂田祐』である。
坂田院長の召天記念日の12月16日に、そして1月27日の中学関東学院創立百年を前に出せたことは最高の喜びであると述べている。坂田は中村から養子に出た関係から坂田をめぐる系図が説明され、そのルーツを説明された。
この書の構成は10話からなるもので、第一話は白虎隊隊長の外孫中村祐から始まって、軍人になるまでの話、軍人中村祐が基督者に、中村から坂田へ、東京帝国大学を37歳で卒業、白雨会坂田、関東学院と坂田、三大難事、命拾いした坂田、見たり聞いたりした坂田、そして十話は坂田日記よりという内容になっている。
発表内容は創立36周年記念式式辞、大学礼拝「内村鑑三について」、我学院ノ理想、第1回卒業式式辞と言うように坂田が語った貴重な文章を読み上げた。
坂田の信仰に大きな影響を与えたのは内村であり、関東学院の教員であった鈴木俊郎が20巻の内村鑑三全集を刊行したが、その中で内村の純福音を「それは≪キリストの奇跡的誕生を信じ、キリストのなされた奇蹟を信じ、キリストの十字架上の贖罪を信じ、キリストの復活を信じ、キリストの再臨を信じる信仰であります」と述べている。
坂田は内村から影響を受け、バプテスト派で、教育者であった4つの側面をもった優れた関東学院のリーダーであったと思われる。
(岡部一興 記)
|
|
 410 回 410 回 |
2月 例会報告 |
|
日時: 2019年2月16日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「内村鑑三のキリスト教道徳論の考察
『羅馬書之研究』12~13章を中心に」
講師: 鳴坂 明人 氏 (関東学院六浦中学校・高等学校) |
1900年以降内村は『聖書之研究』発刊による文書伝道と聖書研究を積極的に展開した。内村にとって、第一次世界大戦は思想的大変化をもたらすものであった。
キリスト教における平和回復の希望を抱いていたが、1917年アメリカが参戦したことによって絶望的になった。そのような絶望的な世界を変えるには、キリストがこの世に来りて社会を変えていく以外にないという確信のもとにキリスト再臨を待望する信仰へと駆り立てられた。
彼は再臨信仰に対し熱狂主義的になった信仰者に疑問を抱き、再臨信仰から身を引いた。それ以後、内村が最も精力を注いだのは『ロマ書』の研究であった。1921年1月から60回の連蔵講演を行い、毎回600名以上の出席者を集めた。
今回の発表は、第1章内村鑑三の『『羅馬書之研究』までの経緯、第2章『羅馬書之研究』における内村鑑三のキリスト教道徳の特性、第3章近代日本における内村鑑三のキリスト教道徳の射程の第2節内村鑑三の聖霊理解とキリスト教道徳を扱った。
内村の聖書研究に至る背景は札幌農学校時代、アマスト大学時代、再臨運動時代の3つが決定的出来事であった。
ここでは発表者の意図を十分にまとめられないので、会報で改めて鳴坂氏に論述して頂く予定である。発表の最後の結びにかえての個所を引用することにする。
「内村は『ロマ書』の告げる人間の根源的罪からの解放を実現するためには、まずキリストの十字架の贖罪と聖霊の働きの必要を説く。
聖霊なる神は人間の内に宿り、その人間を霊的状態に導き、道徳がなくとも正義と至上の善を実行する新たな人間に変革されることを開示するのである。」聖霊を宿すキリスト者と社会との関係は、「個人が神の福音によってキリスト者に改造され、そのキリスト者自身の正義の実行に起点を置き、理想社会と日本国を改造し、その間完成を目指すというものである」という。
(岡部一興 記)
|
|
 409 回 409 回 |
1月 例会報告 |
|
日時: 2019年1月19日(土) 14時~ 横浜指路教会
題 : 「賀川ハルと横浜」
講師: 岩田 三枝子 氏 (東京基督教大学准教授) |
賀川ハルは、1888年芝房吉・むらの長女として横須賀で生まれた。14歳の時1年間女中奉公に出た。その後、伯父村岡平吉が経営し、房吉が勤める福音印刷会社(神戸)で女工として働いた。
ハルは村岡夫妻の影響からキリスト教に触れた。1912年賀川と同じようにマイヤースから洗礼を受けた。翌年5月賀川豊彦と結婚、神戸の新川のスラムに入った。
14年賀川がプリンストン神学校に留学すると、ハルは横浜共立女子神学校で学んだ。校長スーザン・A・プラットのもとで勉学に励んだ。神学校は米国婦人一致外国伝道協会(WUMS)から派遣された宣教師によって経営されている神学校で、超教派的な雰囲気の中で熱心に伝道し、バイブル・リーダー養成を目的とするものであった。
神学校のカリキュラムを紹介、神学と一般教養を学ぶなかで、社会活動として工場、孤児院、慈善病院、厚生施設などを訪問、また家庭訪問、日曜学校に関わり、夏休みには福音伝道なる目的でキリスト教伝道の実践活動が組み込まれていた。
ハルは1921年覚醒婦人協会の中心的な発起人となった。その改訂された綱領をみると、
①男女共同の力により新社会を建設。
②女子労働組合運動の促進。
③婦人参政権及び世界平和運動の促進等を掲げて運動を展開した。
関東大震災に際しては、救援のため神戸から東京世田谷の松沢に移転して活動の場所を変えた。賀川の死後は、イエス団理事長として各事業を引き継いだ。1982年94歳召天。最後にハルの現代的意義が説かれた。
①男女共同のパートナーシップのモデルをみた。
②グローバル化のなかで多様な人々と交わる暮らしの在り方を学んだ。
③女性のキャリアを示唆された。
今回の発表はパワーポイントを使った発表で、最後の映像は、オランダのテレビ局が神戸の新川を訪ねて、スラムの面影を残す場面が流れた。賀川は、結核に侵されたことが契機となって新川に入り、残りの人生を神さまから与えられた愛をこの所で実践していきたいと考えてのことであったと思われる。
(岡部一興 記)
|
|
|

